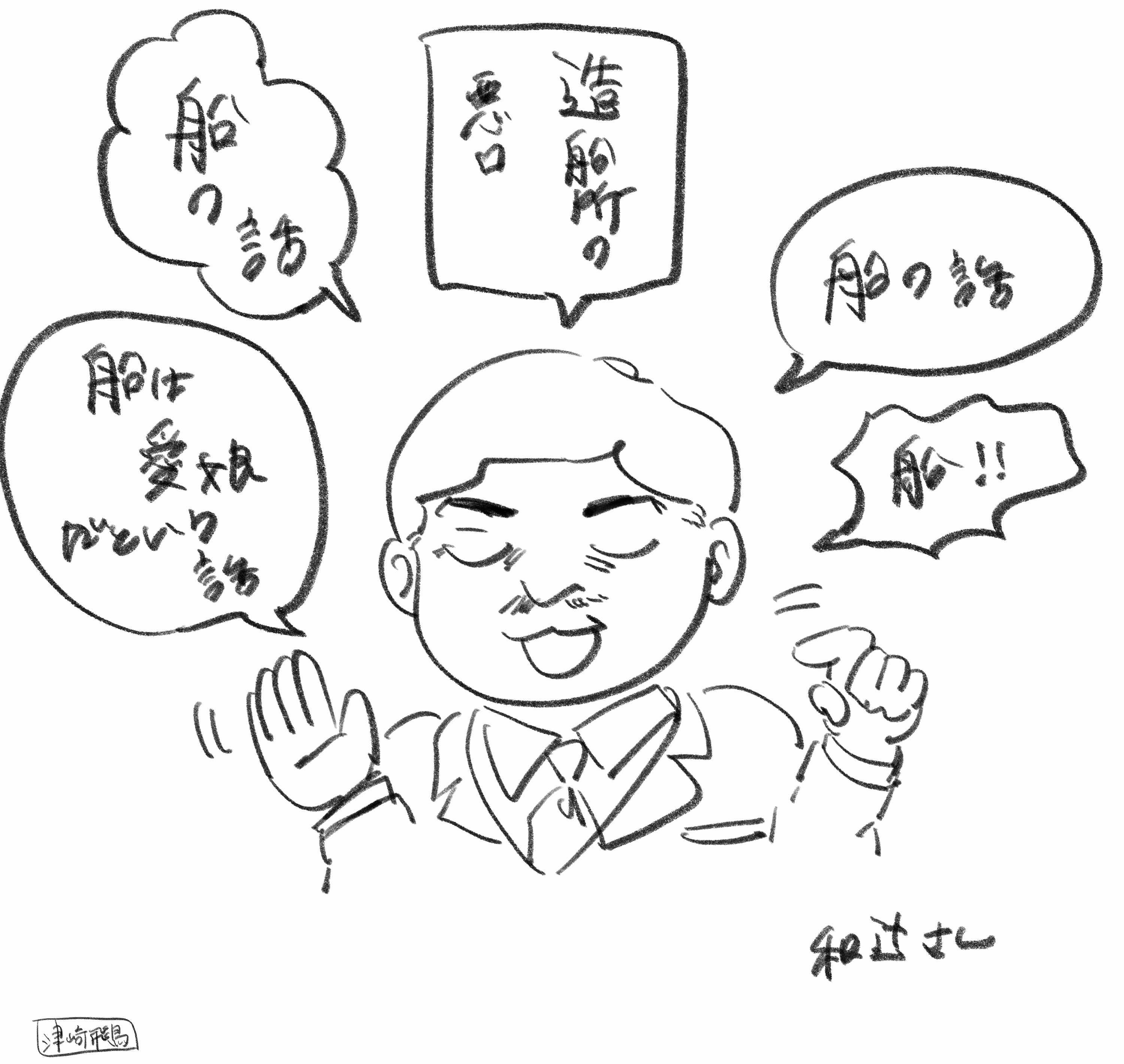良い…と思ったらぜひ押してやってください(連打大歓迎)

いや、冗談ですよ ホント 被害と加害に主体性を見出していく🫰✨ため
原理主義者は日本近代のおおよそは「黒船が来航したのが悪い」で結論つけてるため、戦艦ミズーリの降伏文書調印の時にアメリカがわざわざ「黒船来航時に使った星条旗」を持ってきたことにいっとう意義を見出している
#「渺渺録」(企業擬人化)
#「渺渺録」(企業擬人化)
個人的にはペリーに蒸気機関車の模型をプレゼントされたという逸話が大好きなのでもっと調べたい のちに近代に到る日本国への贈りものであり呪いじゃん、こんなの…
模型というべきかなんというか 小さい蒸気機関車らしく、実際動いたらしいが 詳細は知らない
#「渺渺録」(企業擬人化)
模型というべきかなんというか 小さい蒸気機関車らしく、実際動いたらしいが 詳細は知らない
#「渺渺録」(企業擬人化)
横浜開港資料館に江戸時代の人が外国船(と掲げた信号旗)を正確に転写した絵があって感動したし、「しっかり描いているが、この時代の日本には信号旗という概念がなかった」「描いている人=日本人は後世になって自分らもこの旗の秩序の下の海にいることになると思わなかっただろう」と感じた
「アレがなんだかさっぱりわからない」が「とにかく正確に仔細を転写している」状況にヘキを感じるんだけど、上手く言葉にできない
「後世、自分たちがあれを理解して使うようになる」の黎明を見たからかなぁ
「アレがなんだかさっぱりわからない」が「とにかく正確に仔細を転写している」状況にヘキを感じるんだけど、上手く言葉にできない
「後世、自分たちがあれを理解して使うようになる」の黎明を見たからかなぁ
「特殊潜航艇、小型魚雷艇などの特攻兵器製作に最後の活路を見いだそうと努めた 」三菱重工業(長崎造船所)は震洋(特攻兵器。小型の体当たりボート)も作っています。前々から気には留めていたのですが、先日デジコレ個人送信限定配信の本に震洋会の編纂した『人間兵器震洋特別攻撃隊 写真集』上巻と下巻(国書刊行会刊行)という本があることに気づきました。気になっています。写真集というのは大きい…。
#「渺渺録」(企業擬人化)
#「渺渺録」(企業擬人化)
アウステルリッツがこうした思索を話しながら纏め、いわばとりとめのない思いつきからこのうえなく端整な文章をつむぎ出し、さらに彼にとって専門知識を語り伝えることが、一種の歴史の形而上学へのゆるやかなアプローチになっている――そしてそこでは想起されたものがいまひとたび生命をもって甦る――ことであった。
/『アウステルリッツ』
/『アウステルリッツ』
『沖縄県史』「沖縄戦記録」1と2(9巻と10巻)では
◎方法的には連続性がない
◎1は話者の口調を最大限に生かそうとした
対して、2は録音された口述を、執筆者が特徴的と思える項目に分類して原稿化した
(『沖縄の戦後思想を考える』)
◎方法的には連続性がない
◎1は話者の口調を最大限に生かそうとした
対して、2は録音された口述を、執筆者が特徴的と思える項目に分類して原稿化した
(『沖縄の戦後思想を考える』)
「渺渺録」エピグラフは「七ツ八ツからカンテラ提げて 坑内下がるも親の罰」にしたいんですけど、一つは親=人間の親や先祖や国家、あるいは船にとっての会社・組織、もう一つは子がその系譜にあって、あまりに長く親の親からその体制が続いてきたことで個人一代ではどうにもならなかった時代とその一生を描きたい、という想いで…(ろくろ)
『大脱走』(合冊版)の表紙に「Escape from the old system(旧体制からの逃走)」と書かれているのはご存知でしょうか…
#「渺渺録」(企業擬人化)
『大脱走』(合冊版)の表紙に「Escape from the old system(旧体制からの逃走)」と書かれているのはご存知でしょうか…
#「渺渺録」(企業擬人化)
――ちなみに若松さんの月給はなんと四万円に満たない。若松さんが、踏切小屋に閉じこめられて十年が経った。彼は自戒をこめて次のように語っている
「長い間の奴隷労働からきた会社に対する憎悪の気持と会社を親とする思想とが交錯してすっきりといかなかった。それと同時に与論的なものは古いという考え方とゴンゾーに対するコンプレックスがあって、それらの逃避の思いがからみ合って階級的にぴしっといかなかった。
闘争中一緒に働いた島の仲間が段々と脱落していった。しかしわたしの気持の中には与論のものだけはなんとかまとまって行こうという気持が強かった。そのためいいたいこともいわず同郷者の集まりでもその事はタブーというものがあった。いいたいこともいわないことだけが島のものたちを集団化させていたのかも知れない。そのことは労働者としては妥協ではないかと思うことが度々ある。三池労組でも割れさせないために沈黙するという面がある。それが今の運動を衰退化させ組織の形骸だけを残すという結果になったのかも知れんな。」
そして最後に昨年六月島を訪れた時の後日譚を私たちに開かせてくれた。
「あの時みんなは大歓迎されて感したけどな、島じゃ戦々恐々だったらしいよ。今度大牟田から三池弁議とやらで負けたアカの筋金入りばかりが島にやってくるらしい、ということでな。ところが来てみると、なんともおとなしい。なにもしないで引揚げてくれたということで、島の地政者は、ほっと胸を撫でおろしたそうな」
若松さんは訪島の折、与論を体ぢゅうで感じとりたいと、ひとり海辺に寝ていたのであった。
/森崎和江 川西到『与論島を出た民の歴史』
#「渺渺録」(企業擬人化)
「長い間の奴隷労働からきた会社に対する憎悪の気持と会社を親とする思想とが交錯してすっきりといかなかった。それと同時に与論的なものは古いという考え方とゴンゾーに対するコンプレックスがあって、それらの逃避の思いがからみ合って階級的にぴしっといかなかった。
闘争中一緒に働いた島の仲間が段々と脱落していった。しかしわたしの気持の中には与論のものだけはなんとかまとまって行こうという気持が強かった。そのためいいたいこともいわず同郷者の集まりでもその事はタブーというものがあった。いいたいこともいわないことだけが島のものたちを集団化させていたのかも知れない。そのことは労働者としては妥協ではないかと思うことが度々ある。三池労組でも割れさせないために沈黙するという面がある。それが今の運動を衰退化させ組織の形骸だけを残すという結果になったのかも知れんな。」
そして最後に昨年六月島を訪れた時の後日譚を私たちに開かせてくれた。
「あの時みんなは大歓迎されて感したけどな、島じゃ戦々恐々だったらしいよ。今度大牟田から三池弁議とやらで負けたアカの筋金入りばかりが島にやってくるらしい、ということでな。ところが来てみると、なんともおとなしい。なにもしないで引揚げてくれたということで、島の地政者は、ほっと胸を撫でおろしたそうな」
若松さんは訪島の折、与論を体ぢゅうで感じとりたいと、ひとり海辺に寝ていたのであった。
/森崎和江 川西到『与論島を出た民の歴史』
#「渺渺録」(企業擬人化)
「女の子に母親だけしかおらず、その母が心労たたって病死してしまった時の悲しみ」と、「B-29が飛んできてその空襲で母親が焼死してしまった悲しみ」って、個人からしてみればたぶん同じ感情ではある
ただそれを戦争=ナショナルな事象という枠で俯瞰して時に、語り方には違いが出てくるはずで
ただそれを戦争=ナショナルな事象という枠で俯瞰して時に、語り方には違いが出てくるはずで
じつは私は「兵器という大型機械が思い通りすぐに作動しない」描写が大好きで、高射砲がすぐに旋回しない(「アルキメデスの大戦」冒頭にあった記憶)とか、戦車の主砲を向けるのに手力だと時間がかかる(ガルパンにあった)とか、あるいは航空母艦に向けられた急降下爆撃だって爆弾が当たるまでに乗組員たちには数秒の「ア…!」があったはずで、だからといって筆者がこれが好き!と言ってこだわりを持って描いたとして読者のどれほどがそこに美学を感じてくれるのか謎 まだ感情に訴えた方がいい
あとこの数秒の「ア…!」にまったく関係のない、例えば一人キャンプが好きで時折漫画を読むのが趣味くらいの読者に、もし私がガチガチに知識があったとして仔細を緻密に描写したところで、それが上手く伝わるのか、むしろ一周回って「こんな世界ありえないだろw」にならないのか考えるときはある
『この世界の片隅に』で最後に子どもを拾う描写を「現代的な倫理観で萎える(うろ覚えだけども、こんな感じの大意)」と投稿していた方がいらっしゃって、そんな感じになる可能性もある(当時「戦災孤児を養子にする」のはよくあることだったが、その事実があまり有名ではない)
あとこの数秒の「ア…!」にまったく関係のない、例えば一人キャンプが好きで時折漫画を読むのが趣味くらいの読者に、もし私がガチガチに知識があったとして仔細を緻密に描写したところで、それが上手く伝わるのか、むしろ一周回って「こんな世界ありえないだろw」にならないのか考えるときはある
『この世界の片隅に』で最後に子どもを拾う描写を「現代的な倫理観で萎える(うろ覚えだけども、こんな感じの大意)」と投稿していた方がいらっしゃって、そんな感じになる可能性もある(当時「戦災孤児を養子にする」のはよくあることだったが、その事実があまり有名ではない)
ぼくらの父祖たちにとって国家はどうだったか?それは幻想としての国家像の暗闇であればある程、顕在化する形として女たちの狂気の挿話をとりあげることができる。昭和の十年代、素封家に育った女が、その夫は都市に就職したけれども、女が海を渡るのは当時村では禁忌だった。年月が立つうちに、ついに思いあまって磯の波打際にひざまづいている女の姿が村の誰れそれの眼にも頻繁にみえるようになった。いわば古いしきたりと禁忌によって素封家に生まれた女なのだが、「時間」の推移によって対幻想が危機にさらされるとき素封家の女は美しくしかも近よりがたい狂気と化したのだ。
/『情念の力学』「波打際の論理」
沖縄の自分たちが狂気に囚われた素封家の女のように膝まづきながら海の向こうに渇望したのが、夫であり、都市であり、本土であり、近代であり、国家であった、という認識(だけど、それが正しいのかはわからない)
近代と通ずることができない、という感覚、近代に貫通されない、近代と盃を交わさない、近代と交わらないという感覚、時代を描く時に理解が必要であるというか、
(べつに沖縄がどうとか言いたいのではなくて、)
『攪乱する島』を読めばあの島にちゃんと近代が来ていたことはご理解できると思いますが……軍の装いをした近代が…
近代………
/『情念の力学』「波打際の論理」
沖縄の自分たちが狂気に囚われた素封家の女のように膝まづきながら海の向こうに渇望したのが、夫であり、都市であり、本土であり、近代であり、国家であった、という認識(だけど、それが正しいのかはわからない)
近代と通ずることができない、という感覚、近代に貫通されない、近代と盃を交わさない、近代と交わらないという感覚、時代を描く時に理解が必要であるというか、
(べつに沖縄がどうとか言いたいのではなくて、)
『攪乱する島』を読めばあの島にちゃんと近代が来ていたことはご理解できると思いますが……軍の装いをした近代が…
近代………
日本の大衆が自分自身の日常的思惟様式の欠陥にめざめるためには、在日朝鮮人からの打撃が必要である。私が負ってきた母国との断絶よりも深い傷そのものから、かりものの朝鮮らしさを超えた思想を生みだしてくれることがその一つだ。そのための試行錯誤が、日本人大衆の日常的思惟の世界に対する直接性である時期はなおつづくことだろう。大衆は異相分離ののちの無関心を贖罪だと感じているのだから。また同化の原理以外の対応を知らないから、目の前に立ちあらわれたものとの対応法がわからないぶきみさに、日本はさらされる必要がある。自分のもっていた発想法そのものをゆさぶられるという体験を意識にとどめたものは、敗戦後にやっとかすかに生じたにすぎない。
/「二つのことば・二つのこころ」『精神史の旅 1産土 森崎和江コレクション』
/「二つのことば・二つのこころ」『精神史の旅 1産土 森崎和江コレクション』
いま一つは、国家の「壊疽」になろうとする主張です。この主張を新川さんは、「あたかも壊疽のように、〈国家としての日本〉を内側から腐蝕し」とも、「国家としての日本に対する決定的な「毒」としての沖縄の存在を思想化する」とも表現しています。同化の対極に立とうとする思想というべく、ここに至って反復帰論は、「反国家としての兇区」として完結します。
/『沖縄の戦後思想を考える』
/『沖縄の戦後思想を考える』
〈いっちゃん、また関東大震災のような大きな地震が起こったら、朝鮮人は虐殺されるかしら。一円五十銭、十円五十銭と言わされて竹槍で突つかれるかしら。でも今度はそんなこと起こらないと思うの、あの頃とは世の中の事情が違っているもの。それにほとんどが日本人と全く同じように発音できるもの。ね、いっちゃん、それでも殺されることになったら、私を恋人だってしっかり抱きしめて、私と、私と一緒にいてくれる?いえ、今度は絶対に虐殺なんてされません。でもそれでは困る、私を殺してくれなくちゃあ。私は逃げ惑うの、その後ろを狂った日本人が竹槍や日本刀を持って追いかけてくるわ、私は逃げきれなくて、背中をぐさっと刺されて、胸も刺されて血だらけになってのたうち廻るの。いっちゃん、あれは痛いのね、とっても――この間いっちゃんが研いだ包丁を掴んでみた。そしたら身体がびりびりとしびれて興奮してきて、まるでセックスをしている時のような気持ちになったわ。私、自分が何故お料理が嫌いなのか解ったような気がした。恐いのよ、あのびりびりした感じがたまらなかったのよ。それでね、その包丁で胸のところと手首を切りつけてみたの。痛かった。それに血が、本当にわっと出てくるんだもの。ぐさりとやってみたかったけれど、もっと血が出るのかと思うと恐くなって――今度は金槌で脚を叩いてみたわ、そしたらやっぱり痛かった。ねえ、いっちゃん、私は虐殺されるかしら、ねえ、どうなるの、もしも殺されなかったら、私は日本人なわけ?でもどうしよう、あれは痛いものね、血がいっぱい出るんだものね〉
/李良枝「かずきめ」『由煕 ナビ・タリョン』
/李良枝「かずきめ」『由煕 ナビ・タリョン』
昨日言及した「地獄」とか、「七ツ八ツからカンテラ提げて 坑内下がるも親の罰」(「ゴットン節」)の「親の罰」とか、当時の人々(特に炭鉱や廓に居た人)が現状を精一杯表現した言葉がこれらであって、今仔細を語るとしたら近代資本とか家父長制とかになるんだろか
#「渺渺録」(企業擬人化)
#「渺渺録」(企業擬人化)
「ここは地獄の一丁目や。三丁目のほうがまだよか」という証言があって(『鋼鉄産業の闇』)、こういうの、無条件に好きだ
炭坑や製鉄所みたいな身体を張った産業にいる人々、あるいは身体を売っていた娼妓たちの言う、罵倒と半笑いの自嘲と屈折した矜持みたいなものを孕ませた「地獄」(間違いなく「おい地獄さ行ぐんだで!」文脈の地獄)についての解題、もっと読みたいな…
身体を張って働いては地獄!狐の祟り!みたいなことを言って崇めては怖れている「民衆」に、いかに企業とその人間たちが近代資本思想や産業形態や機械を導入したか、みたいなものが「地獄」思想と共に、森崎和江のエッセイ「浮游魂と祖霊」で触れられていて興味深かった
炭坑や製鉄所みたいな身体を張った産業にいる人々、あるいは身体を売っていた娼妓たちの言う、罵倒と半笑いの自嘲と屈折した矜持みたいなものを孕ませた「地獄」(間違いなく「おい地獄さ行ぐんだで!」文脈の地獄)についての解題、もっと読みたいな…
身体を張って働いては地獄!狐の祟り!みたいなことを言って崇めては怖れている「民衆」に、いかに企業とその人間たちが近代資本思想や産業形態や機械を導入したか、みたいなものが「地獄」思想と共に、森崎和江のエッセイ「浮游魂と祖霊」で触れられていて興味深かった
沖縄の「集団自決」について いわゆる「暴力的な描写」と呼ぶべきもの なので隠します
●F-家族壕。姻戚三家族一九人と死に場所を探しに来た母子二人。
「他人」である母子二人を除き農薬の猫いらず(殺鼠剤)を飲む。三十六歳の男性は、いやがる子どもたちに黒糖をまぜて強引に飲ませるが、のたうち回る子どもを見るにみかねて、壕の前の小屋に火をつけて中に放り入れ、また幼い子は腕をつかまえて防空壕の土壁にたたきつける。男性は苦しむ両親、妻を棍棒でたたいて死なせたあと、自分も猫いらずを飲むが致死量には至らず、一人だけ生き残る。実家と行動を共にした幼子三人を連れた女性は、飲んだ猫いらずで自らも苦しみながら、生後二か月の子を乳房で窒息死させ、死にたくないと泣いて逃げ回る男児は叔父が鎌で首を切りつけて死なせる。彼女の父親は忠魂陣に向かう人たちに「みんな自分の壕に帰って、各自で玉砕しなさい。ご飯を腹いっぱい食べて、きれいな着物を着てやりなさい」と泣きながら話していたという証言がある[宮城(2008)p.120]。この家族は全員死亡。
/宮城晴美「2 座間味島の「集団自決」」『友軍とガマ 沖縄戦の記録 沖縄・問いを立てる4』98p
※[宮城(2008)p.120]=宮城晴美『新版・母の遺したもの――沖縄・座間味島「集団自決」の新しい事実』高文研、2008年。畳む
●F-家族壕。姻戚三家族一九人と死に場所を探しに来た母子二人。
「他人」である母子二人を除き農薬の猫いらず(殺鼠剤)を飲む。三十六歳の男性は、いやがる子どもたちに黒糖をまぜて強引に飲ませるが、のたうち回る子どもを見るにみかねて、壕の前の小屋に火をつけて中に放り入れ、また幼い子は腕をつかまえて防空壕の土壁にたたきつける。男性は苦しむ両親、妻を棍棒でたたいて死なせたあと、自分も猫いらずを飲むが致死量には至らず、一人だけ生き残る。実家と行動を共にした幼子三人を連れた女性は、飲んだ猫いらずで自らも苦しみながら、生後二か月の子を乳房で窒息死させ、死にたくないと泣いて逃げ回る男児は叔父が鎌で首を切りつけて死なせる。彼女の父親は忠魂陣に向かう人たちに「みんな自分の壕に帰って、各自で玉砕しなさい。ご飯を腹いっぱい食べて、きれいな着物を着てやりなさい」と泣きながら話していたという証言がある[宮城(2008)p.120]。この家族は全員死亡。
/宮城晴美「2 座間味島の「集団自決」」『友軍とガマ 沖縄戦の記録 沖縄・問いを立てる4』98p
※[宮城(2008)p.120]=宮城晴美『新版・母の遺したもの――沖縄・座間味島「集団自決」の新しい事実』高文研、2008年。畳む
沖縄の勉強を始めたころ、沖縄戦後史研究を先頭を切って切り拓いておられた大田昌秀さんのもとへ、教えを受けに伺ったことがあります。そのとき大田さんから、カンプーのクェヌクサーという言葉を知っているか、と尋ねられました。わたくしは知らなかった。それにたいし大田さんがカンプーというのは艦砲射撃で、クェヌクサーというのは食い残しだ、生き残った沖縄人はそれなのだ、と強い口調でおっしゃったことを思い起こします。
/『沖縄の戦後思想を考える』
/『沖縄の戦後思想を考える』
とはいえ日本軍の航空史よりはそれこそ郵便航空機のほうがきになる でも海外書籍は言語がね…
感傷的ナショナリズムというか定型ナラティブに固められていない特攻隊員ものとかは読んでみたい
あとは沖縄戦かな でも沖縄戦と自分を接続できない 接続しなきゃいいだけだけれど、沖縄近代史に重要なのは「自分も返り血を浴びる決意」だから…
海もまともに直視してこなかった埼玉県民に沖縄戦の何が…
そもそもアジア・太平洋戦争にばかり焦点を当てること自体が馬鹿馬鹿しいと感じる
感傷的ナショナリズムというか定型ナラティブに固められていない特攻隊員ものとかは読んでみたい
あとは沖縄戦かな でも沖縄戦と自分を接続できない 接続しなきゃいいだけだけれど、沖縄近代史に重要なのは「自分も返り血を浴びる決意」だから…
海もまともに直視してこなかった埼玉県民に沖縄戦の何が…
そもそもアジア・太平洋戦争にばかり焦点を当てること自体が馬鹿馬鹿しいと感じる
艦の「場」は艦内という構造物の中だが、航空機の「場」は海や空にある、みたいなものが… 動きとしては後者が映える気がする
時代のものにおける艦艇は「艦という組織の動き」になってしまい、兵器=艦は「場」「空間」に近いんだけど、その点航空機は人間が兵器=機に密接していて、空や海やほかの人間が近い、という感じがある
死の役割を仏教へ押し付けた神道の、大口を開けたような生の豊穣、生の謳歌、揺蕩うような快楽のようなもの、限れば進水式や漁船へのお祝いに、多くはそこいらの町村の祭りに見られるけど、あの無為な性的享楽と豊穣の紙一重のところに近代日本の解れ、つまり特有の暴力や死があったのかなと時々感じる
この観念を考えるといつも植民地朝鮮から日本へ帰って来た森崎和江が、彼女たちに「まるで何事もなかったように」迎えてくれた日本人のことを「まるきり、くらしの股をひろげている感じで、自分の思惟様式をおしつけてくる」と形容していることを思いだしてしまう 何故だかわからないが…
とはいえ、そういうなんでもかんでもに「負の点」を見出す姿勢も正していきたい…
結局言いたいこと?「「渺渺録」で漁船のお祝いでも描けないかな~」ということですね
『ねじ曲げられた桜』のあの不思議な読み心地は「桜の枝を身体に飾って微笑んでいる特攻隊員」を語っている所にある、日本近代の果ての死の淵の果てまで来た日本人に飾られるのはやはり平安以来の桜であり、また軍が桜で祝い装うこと位でしか死を美しく包装できなかった日本近代の限界を解題している所に
#「渺渺録」(企業擬人化)
この観念を考えるといつも植民地朝鮮から日本へ帰って来た森崎和江が、彼女たちに「まるで何事もなかったように」迎えてくれた日本人のことを「まるきり、くらしの股をひろげている感じで、自分の思惟様式をおしつけてくる」と形容していることを思いだしてしまう 何故だかわからないが…
とはいえ、そういうなんでもかんでもに「負の点」を見出す姿勢も正していきたい…
結局言いたいこと?「「渺渺録」で漁船のお祝いでも描けないかな~」ということですね
『ねじ曲げられた桜』のあの不思議な読み心地は「桜の枝を身体に飾って微笑んでいる特攻隊員」を語っている所にある、日本近代の果ての死の淵の果てまで来た日本人に飾られるのはやはり平安以来の桜であり、また軍が桜で祝い装うこと位でしか死を美しく包装できなかった日本近代の限界を解題している所に
#「渺渺録」(企業擬人化)
そこに二、三日いる間に、避難民が十人余り雪崩れ込んできたことがありましたね。そこは兵隊の陣地壕ですから、民間人は入れなかったんですよ。それでも、あんまり艦砲が烈しいので、一寸の間だけ入れて下さい、と泣き込んで入ってきたんです。その人たちの中に、子持ちの女の人がいました。その女の人の二歳ぐらいになる男の子供が、あんまり泣き喚くもんだから、兵隊がひどく怒って、叱りつけたんですよ。子供を泣かすなって。それでも子供は泣きやまない。そしたらね、そのお母さんは、子供をつれて出て行ったんですけどね。しばらくしたらそのお母さん一人だけで帰ってきたんですよ。子供をどうしたのか、判りませんけどね。おそらく、子供を捨ててきたと思うんですけどね、そのお母さんも何も言わないし、誰も子供のことを訊こうともしませんでした。
/「旧首里市」『沖縄県史 第9巻(各論編 8 沖縄戦記録 1)』大城志津子氏の証言
#「渺渺録」(企業擬人化)
/「旧首里市」『沖縄県史 第9巻(各論編 8 沖縄戦記録 1)』大城志津子氏の証言
#「渺渺録」(企業擬人化)
検証 戦争に加担した日本文学 (全3冊)
ttps://kachosha.com/books/9784868030249/
① 支配される文学のことば
② 戦中から戦後への〈切断=連続〉
③ ソフト・パワーとしての〈萬葉集〉
『万葉集』というか日本浪漫派がきになる。
日本浪漫派の出征学生たちは『万葉集』を手に戦地に行った、と読んだけど、この美的なロマン主義というものが『ねじ曲げられた桜』で言及されていたもの*1であり…
昔「戦艦大和の最期は非常に美しいと思う反面、美しいで結論付けていいのかとも思う。作戦を決めた海軍の人たちが大和の最期にヒロイズムを持ったのと同じように、私たちもヒロイズムを持つ必要あるか?みたいな……」とXで投稿したことがあるけど、美的なものを美しいと反復する行為は慎重に行いたい
*1
結局、若者たちを特攻という運命に赴かせてしまったものは、彼らの美的価値の希求、つまり彼らのロマン主義と理想主義であったのではなかろうか。彼らは読書を通じて自分たちの世界観と美的価値を作り上げた。もし政府が、軍国主義国家の政治的ナショナリズムをあからさまに正面切って提示していれば、若者たちはこれに反抗することができたであろう。しかし、西洋の高尚な知的伝統という「包装紙」に包み込まれて提示されたので、若者たちは軍国主義政府やインテリ指導者の手になる政治的ナショナリズムを暴くことができなかったのである。
/「序章」『ねじ曲げられた桜 美意識と軍国主義 上』p27(大貫恵美子)
#「渺渺録」(企業擬人化)
ttps://kachosha.com/books/9784868030249/
① 支配される文学のことば
② 戦中から戦後への〈切断=連続〉
③ ソフト・パワーとしての〈萬葉集〉
『万葉集』というか日本浪漫派がきになる。
日本浪漫派の出征学生たちは『万葉集』を手に戦地に行った、と読んだけど、この美的なロマン主義というものが『ねじ曲げられた桜』で言及されていたもの*1であり…
昔「戦艦大和の最期は非常に美しいと思う反面、美しいで結論付けていいのかとも思う。作戦を決めた海軍の人たちが大和の最期にヒロイズムを持ったのと同じように、私たちもヒロイズムを持つ必要あるか?みたいな……」とXで投稿したことがあるけど、美的なものを美しいと反復する行為は慎重に行いたい
*1
結局、若者たちを特攻という運命に赴かせてしまったものは、彼らの美的価値の希求、つまり彼らのロマン主義と理想主義であったのではなかろうか。彼らは読書を通じて自分たちの世界観と美的価値を作り上げた。もし政府が、軍国主義国家の政治的ナショナリズムをあからさまに正面切って提示していれば、若者たちはこれに反抗することができたであろう。しかし、西洋の高尚な知的伝統という「包装紙」に包み込まれて提示されたので、若者たちは軍国主義政府やインテリ指導者の手になる政治的ナショナリズムを暴くことができなかったのである。
/「序章」『ねじ曲げられた桜 美意識と軍国主義 上』p27(大貫恵美子)
#「渺渺録」(企業擬人化)
第一次大戦で製糸業界が混乱した時、工場で工女たちが社長に満期でも帰らないし嫁がないから社長もその意気で居て下さいまし、と言い寄ったという「美談」が残っている、これに対し強制や誘導があったことばかりを強調して、資本の論理を見ることは容易だが、彼女たちのきもちは伝わってこないだろう/彼女たちの労働者・勤労者あるいは生活者としての姿勢がこうした形で表現されているところに、日本の「近代」の荒涼としたかなしさがあり、この哀しさを共有し共感する努力がなければ日本近代史の根底からリアルに把握することはできない/工女や養蚕家など養蚕業の担い手すなわち近代日本の担い手たちは一方的に収奪、搾取され悲惨だったのでなく、まさにその内から歴史を形成してきたこと/彼らは「お国のために」糸を繰ったのではなく生存可能ギリギリの水準を守るために製糸業で働き、人々の必死の労働の成果が「軍事大国」化に動員されていった/『繭と生糸の近代史』
#「渺渺録」(企業擬人化)
#「渺渺録」(企業擬人化)
「軍事大国」の経済的基礎は、軍艦や大砲や帝国議会の動きやらにではなく、指先の技巧で生糸を繰っている少女たちの姿においてこそ現実的に把握されるといわなければならないのである。
/「概観 日本人と生糸」『繭と生糸の近代史』
#「渺渺録」(企業擬人化)
/「概観 日本人と生糸」『繭と生糸の近代史』
#「渺渺録」(企業擬人化)
変革主体の形成を問うと言いながら、その時代を生きた人々に「ないものねだり」をする愚かさについては、言う迄もあるまい。けれども、 「資金調達」や「市場」等々について緻密な研究が積み重さねられていっても、それが養蚕家製糸工女・製糸家その他まさに「生きた人間諸個人」を後景に退けた、いわば「おくれた日本資本主義」の再確認に帰結するのであれば、それは少なくとも私にとっては何の意味もないのである。 歴史を対象とする研究が「歴史としての現代」 に対する責務から解放されてはならないと考える限り、つまりは我々の未来を展望することにいささかなりとかかわりを保とうとする限り、むしろ「おくれた日本資本主義」のなかで、人々がどの様に生き何を形成して来たのか、何を考え、あるいは考えることができなかったのか、そしてそこから人々が単なる「人々」ではない主体として自らを形成する道はどの様に展望されたのか、を問うことにこそ《意味》があるのではあるまいか。
とはいえ、学問研究たらんとする以上、心情主義的に性急に 《意味》を追求するあまり、無意識のうちにも対象化を放棄した「情感の海」にひたる様なことは、厳しく拒絶されなければならない。「人々がどう生きたか」を考えるにしても、課題はあくまでも「まさに構造論と結合した民衆史の形成でなければならない」(石井寛治 「産業革命論」同氏ほか編『近代日本経済史を学ぶ(上)』、一九七七年、八六頁)であろう。私が《意味》 を求めようとした問題を力法として展開しようとしたのが本書の序章第一節であり、以下の諸章はそれなりにその方法をふまえているつもりであるが、それが問題=方法として一貫しているか、ましてや成功しているか否かについては、読者の判断にまつほかない。ここでは、先学諸氏の精緻な研究に比べての実証面での粗雑さをある程度意識しながらも、敢えてこうした形で本書を世に問おうとしたわけを述べておきたかった。もっともこの様な言いぐさは、「ひらき直り」ではあっても「申しひらき」になり得ないことは、私としても充分承知しているつもりである。理論的・実証的に、あらゆる角度からの厳しい批判の寄せられることを覚悟し、かつ期待している。
/瀧澤秀樹「はしがき」『日本資本主義と蚕糸業』
#「渺渺録」(企業擬人化)
とはいえ、学問研究たらんとする以上、心情主義的に性急に 《意味》を追求するあまり、無意識のうちにも対象化を放棄した「情感の海」にひたる様なことは、厳しく拒絶されなければならない。「人々がどう生きたか」を考えるにしても、課題はあくまでも「まさに構造論と結合した民衆史の形成でなければならない」(石井寛治 「産業革命論」同氏ほか編『近代日本経済史を学ぶ(上)』、一九七七年、八六頁)であろう。私が《意味》 を求めようとした問題を力法として展開しようとしたのが本書の序章第一節であり、以下の諸章はそれなりにその方法をふまえているつもりであるが、それが問題=方法として一貫しているか、ましてや成功しているか否かについては、読者の判断にまつほかない。ここでは、先学諸氏の精緻な研究に比べての実証面での粗雑さをある程度意識しながらも、敢えてこうした形で本書を世に問おうとしたわけを述べておきたかった。もっともこの様な言いぐさは、「ひらき直り」ではあっても「申しひらき」になり得ないことは、私としても充分承知しているつもりである。理論的・実証的に、あらゆる角度からの厳しい批判の寄せられることを覚悟し、かつ期待している。
/瀧澤秀樹「はしがき」『日本資本主義と蚕糸業』
#「渺渺録」(企業擬人化)
神ノ池に一つだけ残る掩体壕の中に桜花のレプリカがある。車輪のついた台の上に機体が乗っているのを、桜花の車輪だと思い込んでいた。桜花は着陸しない。従って車輪は必要ない。それに気づいた時、心が震えた。
/『戦争廃墟』
#「渺渺録」(企業擬人化)
/『戦争廃墟』
#「渺渺録」(企業擬人化)
戦争によって故郷へと追いかえされた、と思っているからゆきさんである。兄あるいは弟を「男にしてやりたい」と出稼ぎに行き、幾度かに及ぶ送金で、わずかな田畠であれともかくも自活し、日本土民ふうに根づいているものと思って、その故郷へ帰っている。が、日本の近代化はこの土民志向型のくらしを後進性として位置づけて、帝国主義的国家を確立してきたのである。帰ってみれば日本土民は土民たることに自信を持てなくなっていた。「帰ってこんがましじゃった……」との怒りと悲しみの青音のなかには、実に多面な、思想のカオスのごとき体験がつまっている。アジアへの心のひろがりと国家的侵略。アジア諸民族との接触と戦争。その接触の性のすがた……
[…]
さて、からゆきさんはその苦界を民間外交などとも言って、事実、まことに深部をえぐる外交を心に感じとってきた。それは近親者などへ少なからぬ影響を及ぼしていることを聞き歩きの折々に感じさせられる。が、その体験さえ、侵略戦争とさまざまな形でつながっている。日本が植民地とした朝鮮へ売られ、売られつつなお「日の丸」であったからゆきさんの話をうかがったりもしたけれど、からゆきさんすら一椀のめしを現地の民衆とうばいあう関係のなかにいたのである。
海外にうりとばされ、売春を強要され、身をもちくずして彼の地で果てた少女たちの、その苛酷な生涯に対して、なおそのように言わねばならないところに、庶民の生存と国家の意図との宿敵のような関係がある。それは庶民のナショナリズムそしてインターナショナリズムと、国家のそれとのくっきりとしたちがいが、下層民衆のアジア体験の場に浮き出るからである。
売られることもなく、売春の味も知らずに齢を重ねてしまう私が、からゆきさんと出会うことができる唯一の小道は、彼女らが海の外でアジア諸民族と肌をあわせつつ育てあげた特有な心象世界を、日本への鋭い内部批判として受けとることにある。そしてそれを、彼女らもまたすべての日本民衆と同じように他民族の一椀のめしを叩き落とす存在ともなっていた地点を、見のがしてやるような不遜な立場をつくり出すことなく行うことができるか否か、にある。
/「からゆきさんが抱いた世界」『精神史への旅 3海峡 森崎和江コレクション』
からゆきさんが海をこえだしたころ、九州を中心にして、別の一群がやはり国をではじめていた。志士と自称した人びとである。かれら志士は「諭書」によらずとも、天子サマを君主に奉ずることを生きがいにするナショナリストであった。かれらを大陸浪人とよんだ人もいた。臣としてつかえたい天皇を新政権にひとりじめされて、こころざしをえぬところの、西南の役の敗者たちだった。かれらは波々の身でアジアの現状をしらべて、新君主につくそうとしていた。その意図は純粋で、一般に支配権力に対して野心をもっているわけではなかった。かれらは、政府の政策は、日本をとりまく情況を正しくみていない、西欧に追従していて、国を危機におちいらせるおそれがある、と考えていた。
[…]
次元をまるで異にするこれらふたつのからゆきが、それでも、ふと相まみえたときがあった。海を越えた志士たちは、からゆきさんが働く楼を足がかりにしたのである。
「すすんで志士の世話をし」たと『東亜先覚志士記伝』にある。からゆきさんをかれらは娘子軍とよんだ。
「娘子軍は九州方面の出身の者が多かったが、氷雪肌を劈く西価の購野の奥まで進むに当っても、純然たる日本の服装をなし、僅に一枚のショールを纏うて寒さを凌ぎつつ突進するのが常であった」(『東亜先志士記伝』)
/「天草灘」『精神史への旅 3海峡 森崎和江コレクション』
#「渺渺録」(企業擬人化)
[…]
さて、からゆきさんはその苦界を民間外交などとも言って、事実、まことに深部をえぐる外交を心に感じとってきた。それは近親者などへ少なからぬ影響を及ぼしていることを聞き歩きの折々に感じさせられる。が、その体験さえ、侵略戦争とさまざまな形でつながっている。日本が植民地とした朝鮮へ売られ、売られつつなお「日の丸」であったからゆきさんの話をうかがったりもしたけれど、からゆきさんすら一椀のめしを現地の民衆とうばいあう関係のなかにいたのである。
海外にうりとばされ、売春を強要され、身をもちくずして彼の地で果てた少女たちの、その苛酷な生涯に対して、なおそのように言わねばならないところに、庶民の生存と国家の意図との宿敵のような関係がある。それは庶民のナショナリズムそしてインターナショナリズムと、国家のそれとのくっきりとしたちがいが、下層民衆のアジア体験の場に浮き出るからである。
売られることもなく、売春の味も知らずに齢を重ねてしまう私が、からゆきさんと出会うことができる唯一の小道は、彼女らが海の外でアジア諸民族と肌をあわせつつ育てあげた特有な心象世界を、日本への鋭い内部批判として受けとることにある。そしてそれを、彼女らもまたすべての日本民衆と同じように他民族の一椀のめしを叩き落とす存在ともなっていた地点を、見のがしてやるような不遜な立場をつくり出すことなく行うことができるか否か、にある。
/「からゆきさんが抱いた世界」『精神史への旅 3海峡 森崎和江コレクション』
からゆきさんが海をこえだしたころ、九州を中心にして、別の一群がやはり国をではじめていた。志士と自称した人びとである。かれら志士は「諭書」によらずとも、天子サマを君主に奉ずることを生きがいにするナショナリストであった。かれらを大陸浪人とよんだ人もいた。臣としてつかえたい天皇を新政権にひとりじめされて、こころざしをえぬところの、西南の役の敗者たちだった。かれらは波々の身でアジアの現状をしらべて、新君主につくそうとしていた。その意図は純粋で、一般に支配権力に対して野心をもっているわけではなかった。かれらは、政府の政策は、日本をとりまく情況を正しくみていない、西欧に追従していて、国を危機におちいらせるおそれがある、と考えていた。
[…]
次元をまるで異にするこれらふたつのからゆきが、それでも、ふと相まみえたときがあった。海を越えた志士たちは、からゆきさんが働く楼を足がかりにしたのである。
「すすんで志士の世話をし」たと『東亜先覚志士記伝』にある。からゆきさんをかれらは娘子軍とよんだ。
「娘子軍は九州方面の出身の者が多かったが、氷雪肌を劈く西価の購野の奥まで進むに当っても、純然たる日本の服装をなし、僅に一枚のショールを纏うて寒さを凌ぎつつ突進するのが常であった」(『東亜先志士記伝』)
/「天草灘」『精神史への旅 3海峡 森崎和江コレクション』
#「渺渺録」(企業擬人化)
「渺渺録」で炭鉱も描きたくて、とりわけ、明らかにそこで「脇役」「少数者」ではなかったはずの朝鮮人坑夫を触れるか、示唆するかくらいはしたい。
炭坑の写真を見ていると、日本語の下に同じ意味のハングルの看板が付けられている看板の写真や、日本語/朝鮮語の名札を付けている坑夫の写真などがある。
あと『石炭の文学史』に、"日本語で『爆発するから逃げろ』と叫んでも日本語が分からないのでそのまま巻き込まれる朝鮮人が少なくなかった"と書かれていて、まあ、そういう世界ですよね……
#「渺渺録」(企業擬人化)
炭坑の写真を見ていると、日本語の下に同じ意味のハングルの看板が付けられている看板の写真や、日本語/朝鮮語の名札を付けている坑夫の写真などがある。
あと『石炭の文学史』に、"日本語で『爆発するから逃げろ』と叫んでも日本語が分からないのでそのまま巻き込まれる朝鮮人が少なくなかった"と書かれていて、まあ、そういう世界ですよね……
#「渺渺録」(企業擬人化)
とはいえ映画「冬の螢」とか観てると、日本人の「進出」と同伴していたのは公娼制なのではないか、と強く思う
#「渺渺録」(企業擬人化)
#「渺渺録」(企業擬人化)
いや、「少なくない」わけではないか。あまりに自明すぎて、わかっている人間はあえて強い言葉で明言してないだけだ
戦時下だったら自分も大日本婦人会の襷を掛けて万歳三唱で見送ってたんじゃないか、みたいな想像力が時代を解く上で重要なんじゃないかとよく感じるんだけど、一定の研究書を読むと左記のことが一切考慮されていないものも少なくなくて、しかし研究書というものを書いているのは私より学のある人のはずで…という永遠の循環、ドーナツの穴、ニーベルングの指環…(???)