良い…と思ったらぜひ押してやってください(連打大歓迎)
カテゴリ「随筆・エッセイ」に属する投稿[8件]
2025年9月8日 この範囲を時系列順で読む
2025年7月16日 この範囲を時系列順で読む
#「ノスタルジア 標準語批判序説」(二次創作)
――なぜ夢小説になったのか?
津崎飛鳥(以下、津崎):第一に、私が二次創作で物語を書くのが得意ではないからではないか。具体的にいえば、筆者があえて描かなかった物語の余白を私の拙い描写で埋めることに冒涜と嫌悪を感じる時がある。また、それを感じない時もある。前者と後者には明確な違いがあり、おそらくそれは物語における「視座」の違いのはずだが、これを言語化することに未だ成功はしていない。そのため前者も後者も含まれた二次創作全般に苦手意識がある。
ただ、その苦手な二次創作を描くための明快な解決方法はある。それは原作枠では確実に存在しないし、これからもあり得ない話を描く事だ。たとえば『マーダーボット・ダイアリー』で言うのならば「マルウェアに感染した警備ユニットがグラシンに一目ぼれする」とか、同シリーズの『ネットワーク・エフェクト』時に「ラッティとティアゴが不倫をしていて警備ユニットが満を持して『眼を潰す』」話とか、そんな話を描けばいいのだ。それは筆者があえてえがかなかった余白と余情を勝手に埋める行為でも、筆者のえがく素敵な話に勝手にらくがきを足しているとかでもなく、完全な二次時点での創作だ。それが二次創作というものだ。二次創作をする者はその両者を明確に区別し、自覚的に描くべきではないか、と感じている。また、この提言は筆者の物語にらくがきを描き出す行為が悪だと断じているのではないとは明言しておきたい。この点、夢小説は潔いほど「ありえない話」である。
第二に、「ノスタルジア 標準語批判序説」はいわゆる夢小説というよりは『マーダーボット・ダイアリー』の世界観への所感の文章だ。いくつかのところに記載したが、あれはあの惑星の行政や福祉や「障害」の文章が主体となって構成されているのであって、「推し」キャラと自己が投影されたであるらしい架空キャラとの愉快な関係性の物語ではない。正直そんなものはどうでもいい。いわゆる純粋な「難民」といわれる立場に置かれている登場人物がマーダーボット以外に不在であったために、「障害」を明瞭化することが二次創作では困難だった。警備ユニットは人間の福利厚生など享受しない。医療福祉は人間のものであり、人間的な話でもある。病や貧困の話である。だから結果としてこのような形に落ち着いたまでだ。いわば夢小説とは氾濫した理論と形式のスケープゴートだ。この氾濫は命名により調停される。視座を失い、着地点が曖昧となった物語がたまたま夢小説と名づけられたにすぎない。
――着地点が曖昧となりつつも、物語で目指したものは何か?何度か指し示している「障害」と関係があるのだろうか?
津崎:この物語は、ある種の難題的人生が社会用語へ収斂されていくさま、一個人の文学的ともいえる体験が行政に障害として認定されるさまを想定してえがいた。太宰治の破滅的人生と鬱鬱とした文学的思考が現代の精神医学へ繋がれたときそれは五六文字程度のただの病名として収斂される。収斂までのそれまでの経過は一言で断言しきられる。診断書などによって。あるいは素人の無邪気なレッテル貼りによって。
この物語は「経過」が主題だ。昔の-1から現在の0への移行の間を経過と呼ぶ。0地点から見たその経過を、過去とか、追想とか、栄光とか、思い出とか、昨日の世界などと呼ぶ。それぞれがそれぞれの想いで名前をつけて過去を呼ぶ。主人公は過去を苦々しいベル・エポックと解釈していただろうし、アンは長期間の被虐待経験と呼ぶだろう。企業に雇われていた、灼熱の採掘施設で労働していた、選別台を動かしていた、同僚が殴られていた、集鉱機に落ちて死んでいった、働くことは辛くて熱くて苦しかった、誰かが泣いていた……だがそこには小さな石ころみたいな幸せがあったのだ、労働と幸福が奇妙に結びついていたのだ……という企業リムの世界は、プリザベーション・ステーション警備局の上級局員のインダーによって「企業の奴隷労働者収容所」と定義される。ここで私はヴィクトール・フランクルを想起する。ナチに囚われたユダヤ人の絶対的な強制収容所体験を喚起させる。彼には収容所においての経験がある。そこでも彼は点呼場の前で仲間たちと見た夕暮れの空の美しさを忘れなかった。彼は労働苦役で壕を掘っていた最中でも、外に見た絵画的情景を憶えていた。アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所でも収容者たちは「感動する」という人間的感情を捨てなかったのだ。「奴隷労働者」が「収容所」で見た世界の美しさを、どうしてインダーが否定できよう。精神病既往歴や虐待経験歴を診断書に書かれたとき、誰にかれが「ただの不幸な人間」「かわいそうな人間」だと断定する権利があるだろう。それは他人に対する越権行為である。その行為に対して、自身も理由は分からないが一つの執着を感じている。人間の体験はそのように矮小化されてはならないと感じる。それが個人の負の時代であろうとも。いや負であるからこそ、なのか。
また、この物語を完結させようとしたきっかけは今回の参議院選挙であったために、初期計画であった「障害」のほか、いわゆる「難民」、移民の物語という色も濃く現れた。「ファースト」と呼ばれる人種が存在する、という思想が存在する、という一つの共同体が存在する、ということも念頭に置いて書いた。また、日本語=標準語と生存の関係については、李良枝の愛読者を自負する者として一定の考慮をしたつもりだ。
――内容の出来に自信はあるか?
津崎:夢小説マニアではないので夢小説みを達成しているのかわからないが、一つの小説としては正直、多少なら面白いと思う。
――正直疲れてる?(笑)
津崎:疲れてる(笑笑)普段やってないことをやっている自覚はある。この夢小説もそのひとつにすぎない。いずれにせよ、それを自覚し、自省し、ここから跛行し出発するしかないように、私は思うのだ。
(『文学通 2025年8月号』「『 ノスタルジア 標準語批判序説 』完結にあたって・著者インタビュー」より一部抜粋)
――なぜ夢小説になったのか?
津崎飛鳥(以下、津崎):第一に、私が二次創作で物語を書くのが得意ではないからではないか。具体的にいえば、筆者があえて描かなかった物語の余白を私の拙い描写で埋めることに冒涜と嫌悪を感じる時がある。また、それを感じない時もある。前者と後者には明確な違いがあり、おそらくそれは物語における「視座」の違いのはずだが、これを言語化することに未だ成功はしていない。そのため前者も後者も含まれた二次創作全般に苦手意識がある。
ただ、その苦手な二次創作を描くための明快な解決方法はある。それは原作枠では確実に存在しないし、これからもあり得ない話を描く事だ。たとえば『マーダーボット・ダイアリー』で言うのならば「マルウェアに感染した警備ユニットがグラシンに一目ぼれする」とか、同シリーズの『ネットワーク・エフェクト』時に「ラッティとティアゴが不倫をしていて警備ユニットが満を持して『眼を潰す』」話とか、そんな話を描けばいいのだ。それは筆者があえてえがかなかった余白と余情を勝手に埋める行為でも、筆者のえがく素敵な話に勝手にらくがきを足しているとかでもなく、完全な二次時点での創作だ。それが二次創作というものだ。二次創作をする者はその両者を明確に区別し、自覚的に描くべきではないか、と感じている。また、この提言は筆者の物語にらくがきを描き出す行為が悪だと断じているのではないとは明言しておきたい。この点、夢小説は潔いほど「ありえない話」である。
第二に、「ノスタルジア 標準語批判序説」はいわゆる夢小説というよりは『マーダーボット・ダイアリー』の世界観への所感の文章だ。いくつかのところに記載したが、あれはあの惑星の行政や福祉や「障害」の文章が主体となって構成されているのであって、「推し」キャラと自己が投影されたであるらしい架空キャラとの愉快な関係性の物語ではない。正直そんなものはどうでもいい。いわゆる純粋な「難民」といわれる立場に置かれている登場人物がマーダーボット以外に不在であったために、「障害」を明瞭化することが二次創作では困難だった。警備ユニットは人間の福利厚生など享受しない。医療福祉は人間のものであり、人間的な話でもある。病や貧困の話である。だから結果としてこのような形に落ち着いたまでだ。いわば夢小説とは氾濫した理論と形式のスケープゴートだ。この氾濫は命名により調停される。視座を失い、着地点が曖昧となった物語がたまたま夢小説と名づけられたにすぎない。
――着地点が曖昧となりつつも、物語で目指したものは何か?何度か指し示している「障害」と関係があるのだろうか?
津崎:この物語は、ある種の難題的人生が社会用語へ収斂されていくさま、一個人の文学的ともいえる体験が行政に障害として認定されるさまを想定してえがいた。太宰治の破滅的人生と鬱鬱とした文学的思考が現代の精神医学へ繋がれたときそれは五六文字程度のただの病名として収斂される。収斂までのそれまでの経過は一言で断言しきられる。診断書などによって。あるいは素人の無邪気なレッテル貼りによって。
この物語は「経過」が主題だ。昔の-1から現在の0への移行の間を経過と呼ぶ。0地点から見たその経過を、過去とか、追想とか、栄光とか、思い出とか、昨日の世界などと呼ぶ。それぞれがそれぞれの想いで名前をつけて過去を呼ぶ。主人公は過去を苦々しいベル・エポックと解釈していただろうし、アンは長期間の被虐待経験と呼ぶだろう。企業に雇われていた、灼熱の採掘施設で労働していた、選別台を動かしていた、同僚が殴られていた、集鉱機に落ちて死んでいった、働くことは辛くて熱くて苦しかった、誰かが泣いていた……だがそこには小さな石ころみたいな幸せがあったのだ、労働と幸福が奇妙に結びついていたのだ……という企業リムの世界は、プリザベーション・ステーション警備局の上級局員のインダーによって「企業の奴隷労働者収容所」と定義される。ここで私はヴィクトール・フランクルを想起する。ナチに囚われたユダヤ人の絶対的な強制収容所体験を喚起させる。彼には収容所においての経験がある。そこでも彼は点呼場の前で仲間たちと見た夕暮れの空の美しさを忘れなかった。彼は労働苦役で壕を掘っていた最中でも、外に見た絵画的情景を憶えていた。アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所でも収容者たちは「感動する」という人間的感情を捨てなかったのだ。「奴隷労働者」が「収容所」で見た世界の美しさを、どうしてインダーが否定できよう。精神病既往歴や虐待経験歴を診断書に書かれたとき、誰にかれが「ただの不幸な人間」「かわいそうな人間」だと断定する権利があるだろう。それは他人に対する越権行為である。その行為に対して、自身も理由は分からないが一つの執着を感じている。人間の体験はそのように矮小化されてはならないと感じる。それが個人の負の時代であろうとも。いや負であるからこそ、なのか。
また、この物語を完結させようとしたきっかけは今回の参議院選挙であったために、初期計画であった「障害」のほか、いわゆる「難民」、移民の物語という色も濃く現れた。「ファースト」と呼ばれる人種が存在する、という思想が存在する、という一つの共同体が存在する、ということも念頭に置いて書いた。また、日本語=標準語と生存の関係については、李良枝の愛読者を自負する者として一定の考慮をしたつもりだ。
――内容の出来に自信はあるか?
津崎:夢小説マニアではないので夢小説みを達成しているのかわからないが、一つの小説としては正直、多少なら面白いと思う。
――正直疲れてる?(笑)
津崎:疲れてる(笑笑)普段やってないことをやっている自覚はある。この夢小説もそのひとつにすぎない。いずれにせよ、それを自覚し、自省し、ここから跛行し出発するしかないように、私は思うのだ。
(『文学通 2025年8月号』「『 ノスタルジア 標準語批判序説 』完結にあたって・著者インタビュー」より一部抜粋)
2025年5月24日 この範囲を時系列順で読む
創作情勢の回顧と展望 2022年5月号(コミティア140で頒布したペーパー)
こんにちは。津崎です。
ペーパーに書くことがなくて急いで文章を書いています。いつもは新刊の解題を書いていることが多いので、そんなことを書こうかなぁと思いつつ言語化が難しくもにょもにょ……と思いながら休みをぼんやりとしています。ふねが見てぇな……。ふねの話もみんなとしたい。そして同人誌語りもしたい。
では、ペーパーの本題としての『永遠のいのち』の話をしたいと思います。
COVID-19対策のための規制もだいぶ緩和されたので、初めて感染が拡大した時の非常事態感をすでに思い出せなくなりつつあることに少し驚いています。
「シン・ゴジラ」で濁流に流されていくボートの群れを見て映画館で気持ち悪くなったことがあったのに、あの映像に何も感じなくなってすでに久しいです。すでにシンゴジを「ポスト3.11(東日本大震災)映画」として観ることができなくなっていることに気づきました。たまたまyoutubeで関連動画として出てきた津波に流されている人たちの動画を見てしまった時に感じた「同じ共同体に属している人が死んでいる」というその場限りで単純で危うい悲しみと使命感のようなものを思い出せるのですが、それもすでに実感としてはついてこないです(まあその共同体への高揚感に限っていえば早く忘れた方が良いのですが……)。
新型コロナ文学の多くやこの『永遠のいのち』も、「そんなことがあったなぁ」という、新型コロナ騒動が記録上だけの存在になったことをあらためて確かめるだけのものになるのかもしれません。あるいは脱新型コロナ化した領土から読む、ただの恋愛や日常や人生の物語として読まれる日が来るのかもしれないと思っています。シンゴジはめっちゃ面白いし価値がある優れた映画なんだけど、それはSF要素やメカミリや非実在の実在性を突き詰めている描写がその面白さを担っている気がします。なので脱3.11化した領土から観るシンゴジはやはり映画として面白い。でも、あの流されるボートや瓦礫、防護服、原発、被災民などのディテールへの「理解」が私に(もしかしたらあなたに)できること、それはやはりあの映画を観ることにおいて重要である気がします。それが「理解」できることは私の強みです。強み、というか、経験した不幸の中から見出せる価値の一つ、そう、たぶんそんなのです。
あなたが東日本大震災下の社会を経験したかどうかは知りません。でも新型コロナ下の社会は経験しています。私とあなたは新型コロナの社会を経験しています。
新型コロナ下のディティールが「理解」として通じる時間を共に過ごしています。新型コロナの経験は不幸ですが、この共通の「理解」は価値のあるものだと考えたいのです。
その時に、あなたにふねの話がしたかったのです。
いまの社会の現状の「理解」ができるあなたに、もしかしたら興味や知識の問題でふねの現状は「理解」できないあなたに、新型コロナ下のふねの話がしたかった。
特に商船の現状の話がしたかった。新型コロナで浮き彫りになったことの一つが観光業への打撃でしたから。今回『永遠のいのち』に登場した一定の船たちは観光業に従事しているといっていい船たちでした。観光船もクルーズ客船もお客が減りましたし、運休もしました。少しは仲間が引退しました。世界的にいえば多くの船が感染症の影響で引退して解体現場や船の墓場へと曳かれていきました。新型コロナ対策の制限が緩和されているといえども今後もそれは続くでしょう。多くの船は末路を迎えるでしょう。不本意で。少し早めで。唐突で。実感のない。そんな終わりを。
私はそんな船のいまの話をしたい。
そしていまの船の命題としての永遠の命の話をしたいと思ったのです。
現在の商船に焦点を当てるときに、永遠の命の話をしようと思いました。
正確にいえば「永遠の命」という常に反語で語られてきたものの話をしようと思ったのです。反語として、有限の命の話として。
終わりに曳かれていくかもしれないという不安を抱えている船と、終わりに曳かれていく不安のない船だったものを対比させることによりそれは鮮やかに浮き彫りになるのではないかと考えました。
コロナ禍の飛鳥Ⅱに対して解体されることがない氷川丸が語る「永遠の命」は死ぬことに似ています、そして沈んだことや解体されたこととほぼ同じでした。ふねは海を往ってこそのもの、それはふねの大前提だからです。だから氷川丸は最期への怯えを見せた飛鳥Ⅱに向かって永遠の命が欲しくないかと尋ねます。本当に永遠の命が欲しいのか?本当に?そんなわけないだろう?これは先達なりの応援の言葉です。反語としての提示でした。
ここから飛鳥Ⅱはこの先を見出すのだと思います。また氷川丸以外の多くの現役船たちもそれぞれがそれぞれのきっかけで再び未来を見出していくのでしょう。有限の命の有限の使い方を。シーバス、シーフレンド7。ロサ・アルバ、ゆめはま。マリーン・ルージュ。にっぽん丸。飛鳥Ⅱ。ほかあまたのふねたちも。永遠の鈍りではなく一瞬の燃えるような生を彼らは歩んでいきます。おそらくは。収支と物理的耐久の許す限り。収支といえば、商いのための船という命題も描いたつもりです。存在意義の一つですから。
物語は予兆だけを残して終わりました。来たるべき「未来」を物語にするには2020年-2021年の連載時では早すぎました。ふねたちが、特に物流や観光を商売とする商船たちが経験した不幸の中から何かを見出すことはまだないのでは、仮に見出していたとしてもそれを物語として落とし込むことは時期尚早なのでは、と考えざるを得ませんでした。新型コロナの惨禍はいまも続いているからです。
だから、私はそのまま「そこにある」をとっておくように努めて描きました。あるがままとしてその状況を描いておく。答えは五年後、十年後にわかるかもしれない。未来にこの同人誌を蔵書から見つけて「彼らにそんなこともあったなぁ」と笑ってあげたいのです。十年後の未来で、新型コロナの終息した未来で。彼らが答えをだすことを、未来があることを、五年後十年後があることを確信したいのです。その予兆と私の期待を、この物語から感じ取って頂けたらこれ以上の幸せはありません。そしてなによりも、この物語を、人間たちの感染症のために忌避された船、不安にくれた船、未来を信じられなかった船、存在意義を果たせなかった船、またそれによる経営悪化や赤字という極めて商船的な理由のため、番狂わせで唐突な"終わり"を迎えた船たちに無力ながら捧げたいと思います。この度はお手に取っていただきほんとうにありがとうございました。
こんにちは。津崎です。
ペーパーに書くことがなくて急いで文章を書いています。いつもは新刊の解題を書いていることが多いので、そんなことを書こうかなぁと思いつつ言語化が難しくもにょもにょ……と思いながら休みをぼんやりとしています。ふねが見てぇな……。ふねの話もみんなとしたい。そして同人誌語りもしたい。
では、ペーパーの本題としての『永遠のいのち』の話をしたいと思います。
COVID-19対策のための規制もだいぶ緩和されたので、初めて感染が拡大した時の非常事態感をすでに思い出せなくなりつつあることに少し驚いています。
「シン・ゴジラ」で濁流に流されていくボートの群れを見て映画館で気持ち悪くなったことがあったのに、あの映像に何も感じなくなってすでに久しいです。すでにシンゴジを「ポスト3.11(東日本大震災)映画」として観ることができなくなっていることに気づきました。たまたまyoutubeで関連動画として出てきた津波に流されている人たちの動画を見てしまった時に感じた「同じ共同体に属している人が死んでいる」というその場限りで単純で危うい悲しみと使命感のようなものを思い出せるのですが、それもすでに実感としてはついてこないです(まあその共同体への高揚感に限っていえば早く忘れた方が良いのですが……)。
新型コロナ文学の多くやこの『永遠のいのち』も、「そんなことがあったなぁ」という、新型コロナ騒動が記録上だけの存在になったことをあらためて確かめるだけのものになるのかもしれません。あるいは脱新型コロナ化した領土から読む、ただの恋愛や日常や人生の物語として読まれる日が来るのかもしれないと思っています。シンゴジはめっちゃ面白いし価値がある優れた映画なんだけど、それはSF要素やメカミリや非実在の実在性を突き詰めている描写がその面白さを担っている気がします。なので脱3.11化した領土から観るシンゴジはやはり映画として面白い。でも、あの流されるボートや瓦礫、防護服、原発、被災民などのディテールへの「理解」が私に(もしかしたらあなたに)できること、それはやはりあの映画を観ることにおいて重要である気がします。それが「理解」できることは私の強みです。強み、というか、経験した不幸の中から見出せる価値の一つ、そう、たぶんそんなのです。
あなたが東日本大震災下の社会を経験したかどうかは知りません。でも新型コロナ下の社会は経験しています。私とあなたは新型コロナの社会を経験しています。
新型コロナ下のディティールが「理解」として通じる時間を共に過ごしています。新型コロナの経験は不幸ですが、この共通の「理解」は価値のあるものだと考えたいのです。
その時に、あなたにふねの話がしたかったのです。
いまの社会の現状の「理解」ができるあなたに、もしかしたら興味や知識の問題でふねの現状は「理解」できないあなたに、新型コロナ下のふねの話がしたかった。
特に商船の現状の話がしたかった。新型コロナで浮き彫りになったことの一つが観光業への打撃でしたから。今回『永遠のいのち』に登場した一定の船たちは観光業に従事しているといっていい船たちでした。観光船もクルーズ客船もお客が減りましたし、運休もしました。少しは仲間が引退しました。世界的にいえば多くの船が感染症の影響で引退して解体現場や船の墓場へと曳かれていきました。新型コロナ対策の制限が緩和されているといえども今後もそれは続くでしょう。多くの船は末路を迎えるでしょう。不本意で。少し早めで。唐突で。実感のない。そんな終わりを。
私はそんな船のいまの話をしたい。
そしていまの船の命題としての永遠の命の話をしたいと思ったのです。
現在の商船に焦点を当てるときに、永遠の命の話をしようと思いました。
正確にいえば「永遠の命」という常に反語で語られてきたものの話をしようと思ったのです。反語として、有限の命の話として。
終わりに曳かれていくかもしれないという不安を抱えている船と、終わりに曳かれていく不安のない船だったものを対比させることによりそれは鮮やかに浮き彫りになるのではないかと考えました。
コロナ禍の飛鳥Ⅱに対して解体されることがない氷川丸が語る「永遠の命」は死ぬことに似ています、そして沈んだことや解体されたこととほぼ同じでした。ふねは海を往ってこそのもの、それはふねの大前提だからです。だから氷川丸は最期への怯えを見せた飛鳥Ⅱに向かって永遠の命が欲しくないかと尋ねます。本当に永遠の命が欲しいのか?本当に?そんなわけないだろう?これは先達なりの応援の言葉です。反語としての提示でした。
ここから飛鳥Ⅱはこの先を見出すのだと思います。また氷川丸以外の多くの現役船たちもそれぞれがそれぞれのきっかけで再び未来を見出していくのでしょう。有限の命の有限の使い方を。シーバス、シーフレンド7。ロサ・アルバ、ゆめはま。マリーン・ルージュ。にっぽん丸。飛鳥Ⅱ。ほかあまたのふねたちも。永遠の鈍りではなく一瞬の燃えるような生を彼らは歩んでいきます。おそらくは。収支と物理的耐久の許す限り。収支といえば、商いのための船という命題も描いたつもりです。存在意義の一つですから。
物語は予兆だけを残して終わりました。来たるべき「未来」を物語にするには2020年-2021年の連載時では早すぎました。ふねたちが、特に物流や観光を商売とする商船たちが経験した不幸の中から何かを見出すことはまだないのでは、仮に見出していたとしてもそれを物語として落とし込むことは時期尚早なのでは、と考えざるを得ませんでした。新型コロナの惨禍はいまも続いているからです。
だから、私はそのまま「そこにある」をとっておくように努めて描きました。あるがままとしてその状況を描いておく。答えは五年後、十年後にわかるかもしれない。未来にこの同人誌を蔵書から見つけて「彼らにそんなこともあったなぁ」と笑ってあげたいのです。十年後の未来で、新型コロナの終息した未来で。彼らが答えをだすことを、未来があることを、五年後十年後があることを確信したいのです。その予兆と私の期待を、この物語から感じ取って頂けたらこれ以上の幸せはありません。そしてなによりも、この物語を、人間たちの感染症のために忌避された船、不安にくれた船、未来を信じられなかった船、存在意義を果たせなかった船、またそれによる経営悪化や赤字という極めて商船的な理由のため、番狂わせで唐突な"終わり"を迎えた船たちに無力ながら捧げたいと思います。この度はお手に取っていただきほんとうにありがとうございました。
日本郵船歴史博物館閉館(移転)雑感諸々
日本郵船歴史博物館を初めて訪問したのは二〇一八年前後だと思われる。艦船を追いかけ始めたのは二〇一二年末の頃だったから、そこから数えれば五年も後のことだった。出不精とはいえ、関東の艦船オタクにしてはこの博物館に対してノーマークだったといえる。
恥ずかしながら正直に告白すると、私にとっての「ふね」とは長らく「海軍の艦艇」のことであった。
それは戦史・ミリタリー趣味から始まった「艦船の追いかけ」だったためでもあるし、軍隊という歴史では良くも悪くも著名な存在に対して、海運会社やその仕事や担った文化的価値というものは「ふねの歴史」に関わる存在としては地味なものだったからだ。その「地味」という評価は何かしらの侮蔑や蔑視や軽視ではなく、単純な無知に由来する「初心者には受信できないマイナーな情報」という意味での「地味」だった。
歴史という大河にまったく詳しくなく、なぜその艦が必要とされたのか、軍艦とは何か、海軍の由来は、海軍の意味は、国家の矛と盾としての軍隊とは、当時の時代の日本の様相は、世界の海とは……。あるいは、海運会社が文化面で担った責務とは?貨客船で行いたかった生業とは?そのような世界の展望や横断した知見には程遠い視点で、個々の艦の知識というよりは情報ばかりを己のなかで肥大させていた(この空母の排水量は、艦載機は云々……)。
さらに私の言う「海軍のふね」といえば軍艦――戦艦や航空母艦、巡洋艦――であって、特設監視艇や病院船、あるいは海防艦などでは決してなかった。後者はいわんや無知な人間にはあまりに「地味」すぎた。私にとって艦は美しいものであり、美しければそれで十分で、その艦の基本情報と周りとの関係性が多少分かればそれでよかったのである。戦闘は戦争の華である。戦闘艦は美である。海上護衛などはいくらかの人間が言うように意味も、存在も、実際の任務自体も、ことごとく文字通り地味であり、同時に上記の意味でも「地味」で初心者には理解ができない複雑怪奇なふねの運用方法だったのだ。
そうしてふねの浅瀬で遊んでいるうちに五年が経過した。
何をして海上護衛や徴用船、特設艦船などに興味を持てたのか、日本郵船歴史博物館の初訪問の時期と同じく覚えていない。しかし当たり前だが五年も経過すれば浅瀬も浅瀬なりに広く深くなる。航空母艦隼鷹(貨客船橿原丸が戦時体制により改造され造られた艦)などから入ったような気もするし、あるいは艦艇種別一覧などを読み解いていけば特設艦船など容易に見つけることができよう。病院船などは存在自体は知っていた。特設病院船という日本海軍が元民間船舶に振った種別を私が認識していなかっただけなのだ。
またこの頃になると海軍や艦艇の濃紺深き実直な文化ではなく、千紫万紅を彩る客船文化に目を奪われるようになった。それは地味とは程遠いものであった。茫漠と漂う爛熟した幸福とちりばめられた奢侈な調度品、海の上だからこそなおさら祈らざるを得なかった素朴な平和と友好の念、海を越えた友情の握手――そんなやさしい世界がそこにはあった。
海軍軍人よりも多くの割合で人員が戦死した軍属たちの怨嗟の声は、その華やかであったはずの叙述詩的世界からの転落とその戦地との落差に鮮やかに彩られ、殊更に悲惨に感じられる。
五年を経た私は、海軍の戦闘での敗北のみを悲劇と捉えるほどに軍隊的あるいは単細胞的な美学を持てなくなっていた。
だから海運というものに活路を求めたのは一種の必然だったかもしれない。美しかった生や美しくなるはずだった未来が戦争という災厄により無残にも失われ、軍艦へと装いを変えられて戦場という火の海の中へと向かう元貨客船や元貨物船など(またその乗組員たち)は、私にポストコロニアリズムや越境文学的な離別を容易に彷彿とさせた。それを悲劇と捉えて消費するそこに一種の危うさがなかったといえば嘘になるが、それでも私はそれを自分の命題として受容したのだった。
日本郵船歴史博物館の移転は寂しい。
再開館は二〇二六年予定らしく、その間に展示も図録もない。移転は新築の高層ビルのなかである。今のような天井が高く影の濃い文化財ではない。どうなるのかさっぱり予想がつかない。
それでも建物も博物館も無くならないだけ有り難いのかもしれない。とりあえず私は二〇二六年まで生きのびねば。
日本郵船歴史博物館と日本郵船に、長い感謝を捧げたい。
#日本郵船歴史博物館再開館の軌跡
日本郵船歴史博物館を初めて訪問したのは二〇一八年前後だと思われる。艦船を追いかけ始めたのは二〇一二年末の頃だったから、そこから数えれば五年も後のことだった。出不精とはいえ、関東の艦船オタクにしてはこの博物館に対してノーマークだったといえる。
恥ずかしながら正直に告白すると、私にとっての「ふね」とは長らく「海軍の艦艇」のことであった。
それは戦史・ミリタリー趣味から始まった「艦船の追いかけ」だったためでもあるし、軍隊という歴史では良くも悪くも著名な存在に対して、海運会社やその仕事や担った文化的価値というものは「ふねの歴史」に関わる存在としては地味なものだったからだ。その「地味」という評価は何かしらの侮蔑や蔑視や軽視ではなく、単純な無知に由来する「初心者には受信できないマイナーな情報」という意味での「地味」だった。
歴史という大河にまったく詳しくなく、なぜその艦が必要とされたのか、軍艦とは何か、海軍の由来は、海軍の意味は、国家の矛と盾としての軍隊とは、当時の時代の日本の様相は、世界の海とは……。あるいは、海運会社が文化面で担った責務とは?貨客船で行いたかった生業とは?そのような世界の展望や横断した知見には程遠い視点で、個々の艦の知識というよりは情報ばかりを己のなかで肥大させていた(この空母の排水量は、艦載機は云々……)。
さらに私の言う「海軍のふね」といえば軍艦――戦艦や航空母艦、巡洋艦――であって、特設監視艇や病院船、あるいは海防艦などでは決してなかった。後者はいわんや無知な人間にはあまりに「地味」すぎた。私にとって艦は美しいものであり、美しければそれで十分で、その艦の基本情報と周りとの関係性が多少分かればそれでよかったのである。戦闘は戦争の華である。戦闘艦は美である。海上護衛などはいくらかの人間が言うように意味も、存在も、実際の任務自体も、ことごとく文字通り地味であり、同時に上記の意味でも「地味」で初心者には理解ができない複雑怪奇なふねの運用方法だったのだ。
そうしてふねの浅瀬で遊んでいるうちに五年が経過した。
何をして海上護衛や徴用船、特設艦船などに興味を持てたのか、日本郵船歴史博物館の初訪問の時期と同じく覚えていない。しかし当たり前だが五年も経過すれば浅瀬も浅瀬なりに広く深くなる。航空母艦隼鷹(貨客船橿原丸が戦時体制により改造され造られた艦)などから入ったような気もするし、あるいは艦艇種別一覧などを読み解いていけば特設艦船など容易に見つけることができよう。病院船などは存在自体は知っていた。特設病院船という日本海軍が元民間船舶に振った種別を私が認識していなかっただけなのだ。
またこの頃になると海軍や艦艇の濃紺深き実直な文化ではなく、千紫万紅を彩る客船文化に目を奪われるようになった。それは地味とは程遠いものであった。茫漠と漂う爛熟した幸福とちりばめられた奢侈な調度品、海の上だからこそなおさら祈らざるを得なかった素朴な平和と友好の念、海を越えた友情の握手――そんなやさしい世界がそこにはあった。
海軍軍人よりも多くの割合で人員が戦死した軍属たちの怨嗟の声は、その華やかであったはずの叙述詩的世界からの転落とその戦地との落差に鮮やかに彩られ、殊更に悲惨に感じられる。
五年を経た私は、海軍の戦闘での敗北のみを悲劇と捉えるほどに軍隊的あるいは単細胞的な美学を持てなくなっていた。
だから海運というものに活路を求めたのは一種の必然だったかもしれない。美しかった生や美しくなるはずだった未来が戦争という災厄により無残にも失われ、軍艦へと装いを変えられて戦場という火の海の中へと向かう元貨客船や元貨物船など(またその乗組員たち)は、私にポストコロニアリズムや越境文学的な離別を容易に彷彿とさせた。それを悲劇と捉えて消費するそこに一種の危うさがなかったといえば嘘になるが、それでも私はそれを自分の命題として受容したのだった。
日本郵船歴史博物館の移転は寂しい。
再開館は二〇二六年予定らしく、その間に展示も図録もない。移転は新築の高層ビルのなかである。今のような天井が高く影の濃い文化財ではない。どうなるのかさっぱり予想がつかない。
それでも建物も博物館も無くならないだけ有り難いのかもしれない。とりあえず私は二〇二六年まで生きのびねば。
日本郵船歴史博物館と日本郵船に、長い感謝を捧げたい。
#日本郵船歴史博物館再開館の軌跡
2024年9月22日 この範囲を時系列順で読む
船の越境論
船に感情というものがあったとしたらという観点に立って特設艦船の心情や悲喜を探ってみたいと思う時がある。特設艦船とは軍隊により接収され改造・改装された船のことで、貨客船・貨物船から小型漁船まで多くの船を網羅する。それら船の共通点は戦わないこと、戦うための船ではないことであり、軍の徴用や買収は戦争への参加を押しつけられた切符であった。多くの船にとっては片道切符となった。早々に戦没する宿命だったからである。
戦わない船の戦争。
兵士も民間人も平等の命、一人の人間である。艦が沈んで光栄の上等、船が沈んだら悲しみをもって悼む、という感情はただの感傷であると退けたい。しかしなぜ民間船が、民間船だった艦が戦没することに私は執着するのだろう、と考えた時に思うのは、世界文学への屈折した愛着と、その文学が永遠の命題とする異郷での客死である。あるいはその異郷で経験するさまざまな障害だろうか。自国の常識はそこでは非常識。彼女の話す母国語はそこでは異国語である。移民の彼女はその国に――その海に、その軍隊には容易に同化できなかったかもしれない。そんな二十世紀の人間たちの痛みを同じくアジア・太平洋戦争下の船たちは背負っていたかもしれなかった。馴染んだ横書きの航海日誌ではなく与えられた戦闘詳報で自らの栄光を語るということ。
船は海を往くことが幸せ、とだけ考えれば、こんな甘い郷愁など抱かなかっただろう。道具は使われてこそ価値がある――それが多少違った使い方であろうとも。病院船はそれでもやはり、いやあるいは、だからこそ美しかったはずだ。
けれどそこに船の悲しみを見出してしまうのは、船ぶねの抱く文化の麗しさとそれを基調とする人びとの文化の麗しさにほかならない。それはもちろん貨客船の抱える一等社交室である。そこにあるグランドピアノである。あるいは漁船の上に翻る大漁旗の旗の金刺繍の輝きでも良い。海と共にあった船、と共にあった人びとの抱いてきた素朴な民衆文化は戦火で荼毘に付すにはあまりに惜しいものだった。
あえてその喪失に美学を見出すこともできただろう。オフィーリアはさいごに水死するから美しいのだ。立ち上がって再び陸に上がることなど到底許されない。あの横たわる退廃的な死のにおい、微睡みにも似た死への緩やかな移行の情景は、憧憬を伴って生者である私たちの想像力を豊かに刺激する。貨客船香取丸はインドネシア海域で雷撃を受け海へと傾斜したとき、サロンにあった大型ピアノが大きな不協和音を奏でながら滑っていった、という……。太平洋戦争開戦すぐの出来事であった。船は陸軍に徴用されていて、陸軍部隊が乗船していた。が、未だ船内には乗組員や平時の物資が乗っていた。そのピアノはかつての栄光を留めているもののひとつだった。船と一緒に海へと転がり落ちてゆく陸軍兵士、乗組員、ピアノ、かつての栄光。沈没したその日はクリスマス・イブであった。
二律背反たる船の生と船の死という命題は、戦場の船というものを仰ぎ見るときにいちばんの難題となって私たちの心を刺すのだろう。生の鮮やかさと死の沈黙。それは人間を見るときも同様である。人間とおなじようにふねを見るということ。人間のうつわとしてのふね。
人間の様相を写すものとしてふねを見定めていきたい。
船に感情というものがあったとしたらという観点に立って特設艦船の心情や悲喜を探ってみたいと思う時がある。特設艦船とは軍隊により接収され改造・改装された船のことで、貨客船・貨物船から小型漁船まで多くの船を網羅する。それら船の共通点は戦わないこと、戦うための船ではないことであり、軍の徴用や買収は戦争への参加を押しつけられた切符であった。多くの船にとっては片道切符となった。早々に戦没する宿命だったからである。
戦わない船の戦争。
兵士も民間人も平等の命、一人の人間である。艦が沈んで光栄の上等、船が沈んだら悲しみをもって悼む、という感情はただの感傷であると退けたい。しかしなぜ民間船が、民間船だった艦が戦没することに私は執着するのだろう、と考えた時に思うのは、世界文学への屈折した愛着と、その文学が永遠の命題とする異郷での客死である。あるいはその異郷で経験するさまざまな障害だろうか。自国の常識はそこでは非常識。彼女の話す母国語はそこでは異国語である。移民の彼女はその国に――その海に、その軍隊には容易に同化できなかったかもしれない。そんな二十世紀の人間たちの痛みを同じくアジア・太平洋戦争下の船たちは背負っていたかもしれなかった。馴染んだ横書きの航海日誌ではなく与えられた戦闘詳報で自らの栄光を語るということ。
船は海を往くことが幸せ、とだけ考えれば、こんな甘い郷愁など抱かなかっただろう。道具は使われてこそ価値がある――それが多少違った使い方であろうとも。病院船はそれでもやはり、いやあるいは、だからこそ美しかったはずだ。
けれどそこに船の悲しみを見出してしまうのは、船ぶねの抱く文化の麗しさとそれを基調とする人びとの文化の麗しさにほかならない。それはもちろん貨客船の抱える一等社交室である。そこにあるグランドピアノである。あるいは漁船の上に翻る大漁旗の旗の金刺繍の輝きでも良い。海と共にあった船、と共にあった人びとの抱いてきた素朴な民衆文化は戦火で荼毘に付すにはあまりに惜しいものだった。
あえてその喪失に美学を見出すこともできただろう。オフィーリアはさいごに水死するから美しいのだ。立ち上がって再び陸に上がることなど到底許されない。あの横たわる退廃的な死のにおい、微睡みにも似た死への緩やかな移行の情景は、憧憬を伴って生者である私たちの想像力を豊かに刺激する。貨客船香取丸はインドネシア海域で雷撃を受け海へと傾斜したとき、サロンにあった大型ピアノが大きな不協和音を奏でながら滑っていった、という……。太平洋戦争開戦すぐの出来事であった。船は陸軍に徴用されていて、陸軍部隊が乗船していた。が、未だ船内には乗組員や平時の物資が乗っていた。そのピアノはかつての栄光を留めているもののひとつだった。船と一緒に海へと転がり落ちてゆく陸軍兵士、乗組員、ピアノ、かつての栄光。沈没したその日はクリスマス・イブであった。
二律背反たる船の生と船の死という命題は、戦場の船というものを仰ぎ見るときにいちばんの難題となって私たちの心を刺すのだろう。生の鮮やかさと死の沈黙。それは人間を見るときも同様である。人間とおなじようにふねを見るということ。人間のうつわとしてのふね。
人間の様相を写すものとしてふねを見定めていきたい。
2024年6月24日 この範囲を時系列順で読む
#「大脱走」(企業擬人化)

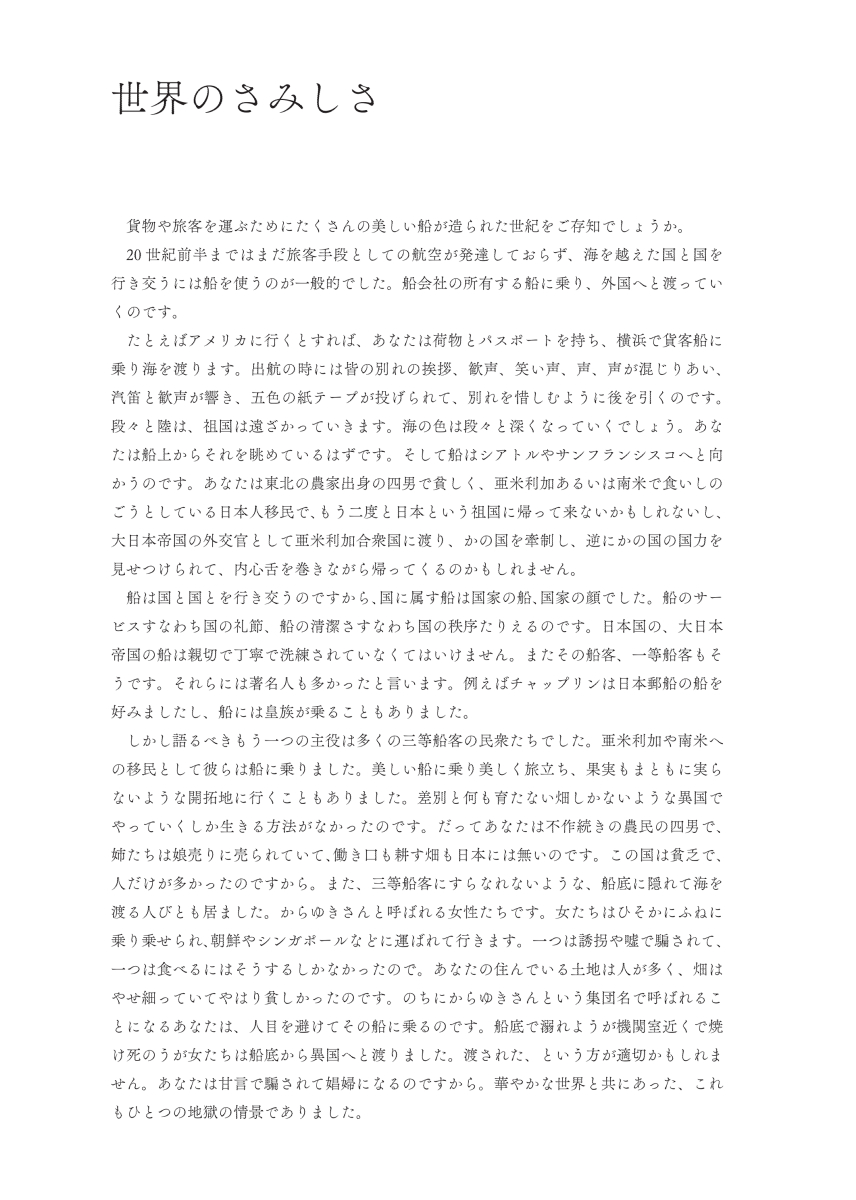
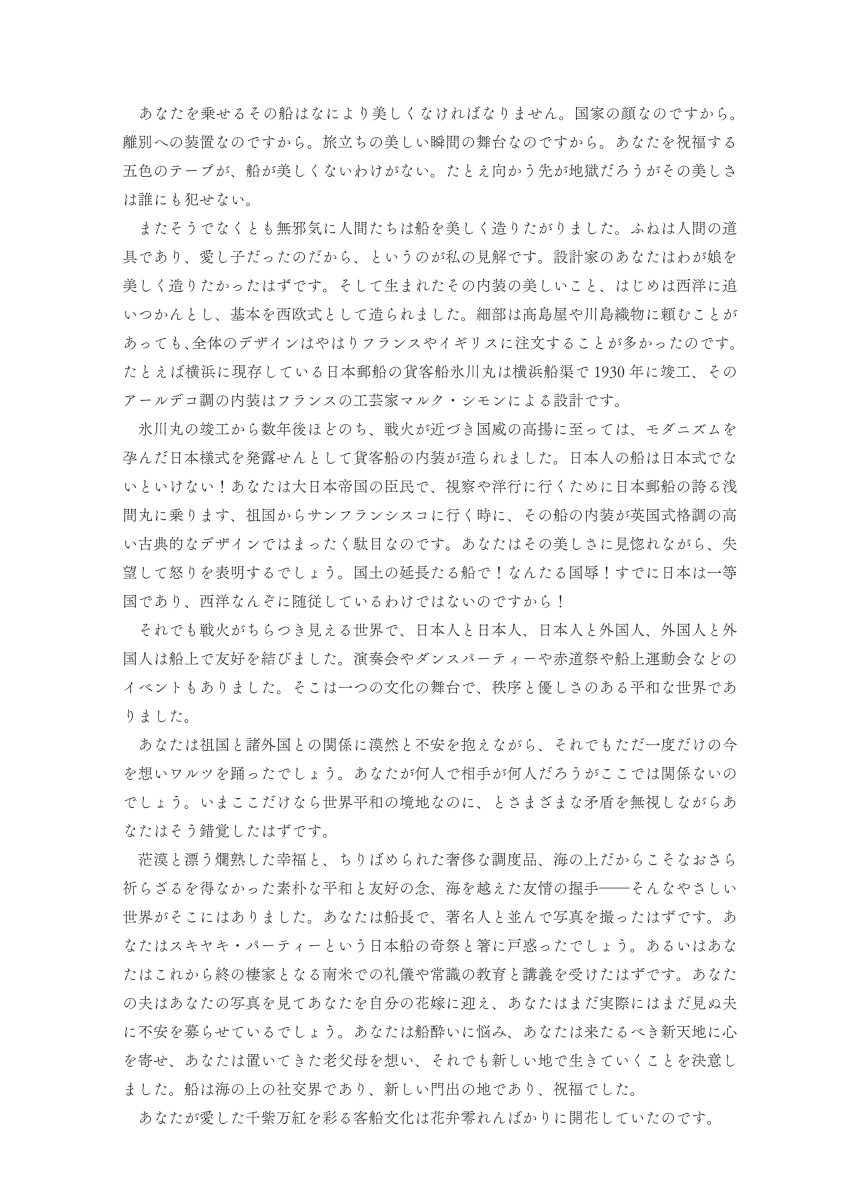
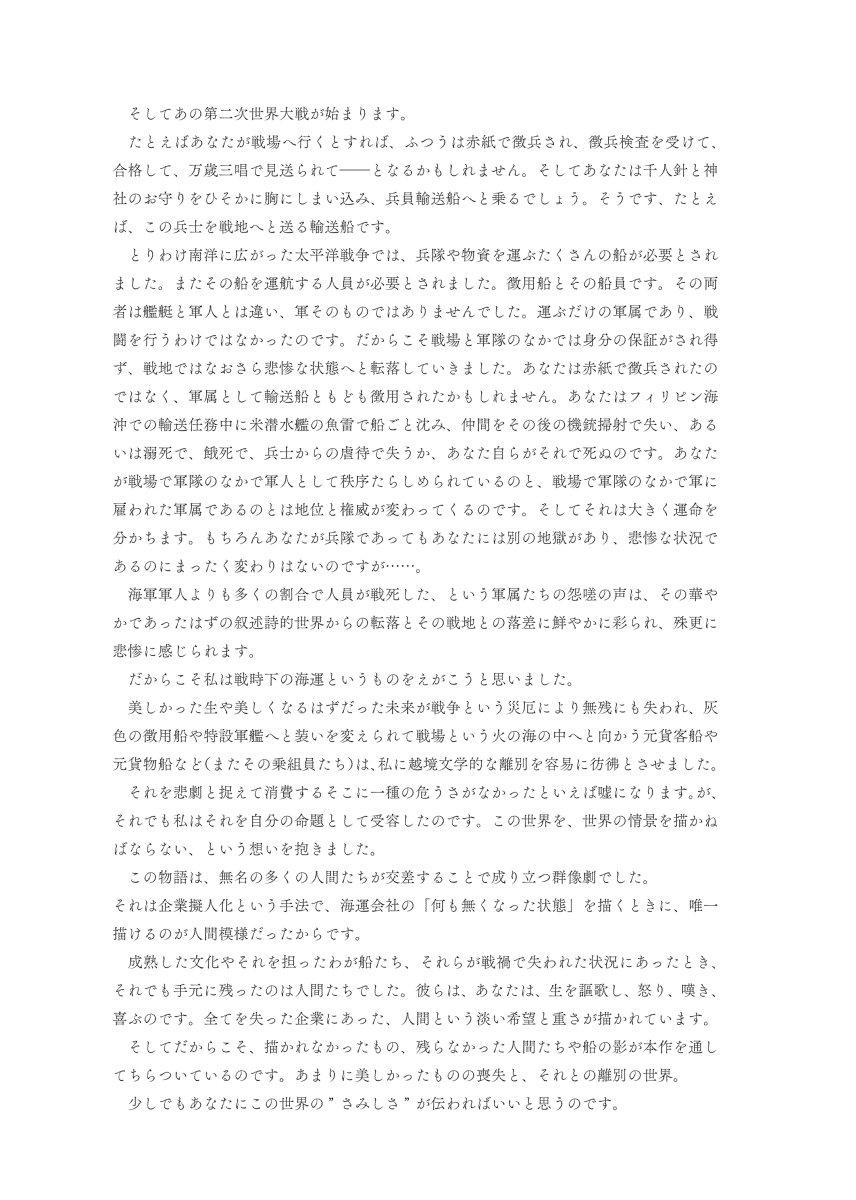
畳む
世界のさみしさ
貨物や旅客を運ぶためにたくさんの美しい船が造られた世紀をご存知でしょうか。
20世紀前半まではまだ旅客手段としての航空が発達しておらず、海を越えた国と国を行き交うには船を使うのが一般的でした。船会社の所有する船に乗り、外国へと渡っていくのです。
たとえばアメリカに行くとすれば、あなたは荷物とパスポートを持ち、横浜で貨客船に乗り海を渡ります。出航の時には皆の別れの挨拶、歓声、笑い声、声、声が混じりあい、汽笛と歓声が響き、五色の紙テープが投げられて、別れを惜しむように後を引くのです。段々と陸は、祖国は遠ざかっていきます。海の色は段々と深くなっていくでしょう。あなたは船上からそれを眺めているはずです。そして船はシアトルやサンフランシスコへと向かうのです。あなたは東北の農家出身の四男で貧しく、亜米利加あるいは南米で食いしのごうとしている日本人移民で、もう二度と日本という祖国に帰って来ないかもしれないし、大日本帝国の外交官として亜米利加合衆国に渡り、かの国を牽制し、逆にかの国の国力を見せつけられて、内心舌を巻きながら帰ってくるのかもしれません。
船は国と国とを行き交うのですから、国に属す船は国家の船、国家の顔でした。船のサービスすなわち国の礼節、船の清潔さすなわち国の秩序たりえるのです。日本国の、大日本帝国の船は親切で丁寧で洗練されていなくてはいけません。またその船客、一等船客もそうです。それらには著名人も多かったと言います。例えばチャップリンは日本郵船の船を好みましたし、船には皇族が乗ることもありました。
しかし語るべきもう一つの主役は多くの三等船客の民衆たちでしょう。亜米利加や南米への移民として彼らは船に乗りました。美しい船に乗り美しく旅立ち、果実もまともに実らないような開拓地に行くこともありました。差別と何も育たない畑しかないような異国でやっていくしか生きる方法がなかったのです。だってあなたは不作続きの農民の四男で、姉たちは娘売りに売られていて、働き口も耕す畑も日本には無いのです。この国は貧乏で、人だけが多かったのですから。また、三等船客にすらなれないような、船底に隠れて海を渡る人びとも居ました。からゆきさんと呼ばれる女性たちです。女たちはひそかにふねに乗り乗せられ、朝鮮やシンガポールなどに運ばれて行きます。一つは誘拐や嘘で騙されて、一つは食べるにはそうするしかなかったので。あなたの住んでいる土地は人が多く、畑はやせ細っていてやはり貧しかったのです。のちにからゆきさんという集団名で呼ばれることになるあなたは、人目を避けてその船に乗るのです。船底で溺れようが機関室近くで焼け死のうが女たちは船底から異国へと渡りました。渡された、という方が適切かもしれません。あなたは甘言で騙されて娼婦になるのですから。華やかな世界と共にあった、これもひとつの地獄の情景でありました。
あなたを乗せるその船はなにより美しくなければなりません。国家の顔なのですから。離別への装置なのですから。旅立ちの美しい瞬間の舞台なのですから。あなたを祝福する五色のテープが、船が美しくないわけがない。たとえ向かう先が地獄だろうがその美しさは誰にも犯せない。
またそうでなくとも無邪気に人間たちは船を美しく造りたがりました。ふねは人間の道具であり、愛し子だったのだから、というのが私の見解です。設計家のあなたはわが娘を美しく造りたかったはずです。そして生まれたその内装の美しいこと、はじめは西洋に追いつかんとし、基本を西欧式として造られました。細部は髙島屋や川島織物に頼むことがあっても、全体のデザインはやはりフランスやイギリスに注文することが多かったのです。たとえば横浜に現存している日本郵船の貨客船氷川丸は横浜船渠で1930年に竣工、そのアールデコ調の内装はフランスの工芸家マルク・シモンによる設計です。
氷川丸の竣工から数年後ほどのち、戦火が近づき国威の高揚に至っては、モダニズムを孕んだ日本様式を発露せんとして貨客船の内装が造られました。日本人の船は日本式でないといけない!あなたは大日本帝国の臣民で、視察や洋行に行くために日本郵船の誇る浅間丸に乗ります、祖国からサンフランシスコに行く時に、その船の内装が英国式格調の高い古典的なデザインではまったく駄目なのです。あなたはその美しさに見惚れながら、失望して怒りを表明するでしょう。国土の延長たる船で!なんたる国辱!すでに日本は一等国であり、西洋なんぞに随従しているわけではないのですから!
それでも戦火がちらつき見える世界で、日本人と日本人、日本人と外国人、外国人と外国人は船上で友好を結びました。演奏会やダンスパーティーや赤道祭や船上運動会などのイベントもありました。そこは一つの文化の舞台で、秩序と優しさのある平和な世界でありました。
あなたは祖国と諸外国との関係に漠然と不安を抱えながら、それでもただ一度だけの今を想いワルツを踊ったでしょう。あなたが何人で相手が何人だろうがここでは関係ないのでしょう。いまここだけなら世界平和の境地なのに、とさまざまな矛盾を無視しながらあなたはそう錯覚したはずです。
茫漠と漂う爛熟した幸福と、ちりばめられた奢侈な調度品、海の上だからこそなおさら祈らざるを得なかった素朴な平和と友好の念、海を越えた友情の握手――そんなやさしい世界がそこにはありました。あなたは船長で、著名人と並んで写真を撮ったはずです。あなたはスキヤキ・パーティーという日本船の奇祭と箸に戸惑ったでしょう。あるいはあなたはこれから終の棲家となる南米での礼儀や常識の教育と講義を受けたはずです。あなたの夫はあなたの写真を見てあなたを自分の花嫁に迎え、あなたはまだ実際にはまだ見ぬ夫に不安を募らせているでしょう。あなたは船酔いに悩み、あなたは来たるべき新天地に心を寄せ、あなたは置いてきた老父母を想い、それでも新しい地で生きていくことを決意しました。船は海の上の社交界であり、新しい門出の地であり、祝福でした。
あなたが愛した千紫万紅を彩る客船文化は花弁零れんばかりに開花していたのです。
そしてあの第二次世界大戦が始まります。
たとえばあなたが戦場へ行くとすれば、ふつうは赤紙で徴兵され、徴兵検査を受けて、合格して、万歳三唱で見送られて――となるかもしれません。そしてあなたは千人針と神社のお守りをひそかに胸にしまい込み、兵員輸送船へと乗るでしょう。そうです、たとえば、この兵士を戦地へと送る輸送船です。
とりわけ南洋に広がった太平洋戦争では、兵隊や物資を運ぶたくさんの船が必要とされました。またその船を運航する人員が必要とされました。徴用船とその船員です。その両者は艦艇と軍人とは違い、軍そのものではありませんでした。運ぶだけの軍属であり、戦闘を行うわけではなかったのです。だからこそ戦場と軍隊のなかでは身分の保証がされ得ず、戦地ではなおさら悲惨な状態へと転落していきました。あなたは赤紙で徴兵されたのではなく、軍属として輸送船ともども徴用されたかもしれません。あなたはフィリピン海沖での輸送任務中に米潜水艦の魚雷で船ごと沈み、仲間をその後の機銃掃射で失い、あるいは溺死で、餓死で、兵士からの虐待で失うか、あなた自らがそれで死ぬのです。あなたが戦場で軍隊のなかで軍人として秩序たらしめられているのと、戦場で軍隊のなかで軍に雇われた軍属であるのとは地位と権威が変わってくるのです。そしてそれは大きく運命を分かちます。もちろんあなたが兵隊であってもあなたには別の地獄があり、悲惨な状況であるのにまったく変わりはないのですが……。
海軍軍人よりも多くの割合で人員が戦死した、という軍属たちの怨嗟の声は、その華やかであったはずの叙述詩的世界からの転落とその戦地との落差に鮮やかに彩られ、殊更に悲惨に感じられます。
だからこそ私は戦時下の海運というものをえがこうと思いました。
美しかった生や美しくなるはずだった未来が戦争という災厄により無残にも失われ、灰色の徴用船や特設軍艦へと装いを変えられて戦場という火の海の中へと向かう元貨客船や元貨物船など(またその乗組員たち)は、私に越境文学的な離別を容易に彷彿とさせました。
それを悲劇と捉えて消費するそこに一種の危うさがなかったといえば嘘になります。が、それでも私はそれを自分の命題として受容したのです。この世界を、世界の情景を描かねばならない、という想いを抱きました。
この物語は、無名の多くの人間たちが交差することで成り立つ群像劇でした。
それは企業擬人化という手法で、海運会社の「何も無くなった状態」を描くときに、唯一描けるのが人間模様だったからです。
成熟した文化やそれを担ったわが船たち、それらが戦禍で失われた状況にあったとき、それでも手元に残ったのは人間たちでした。彼らは、あなたは、生を謳歌し、怒り、嘆き、喜ぶのです。全てを失った企業にあった、人間という淡い希望と重さが描かれています。
そしてだからこそ、描かれなかったもの、残らなかった人間たちや船の影が本作を通してちらついているのです。あまりに美しかったものの喪失と、それとの離別の世界。
少しでもあなたにこの世界の”さみしさ”が伝わればいいと思うのです。

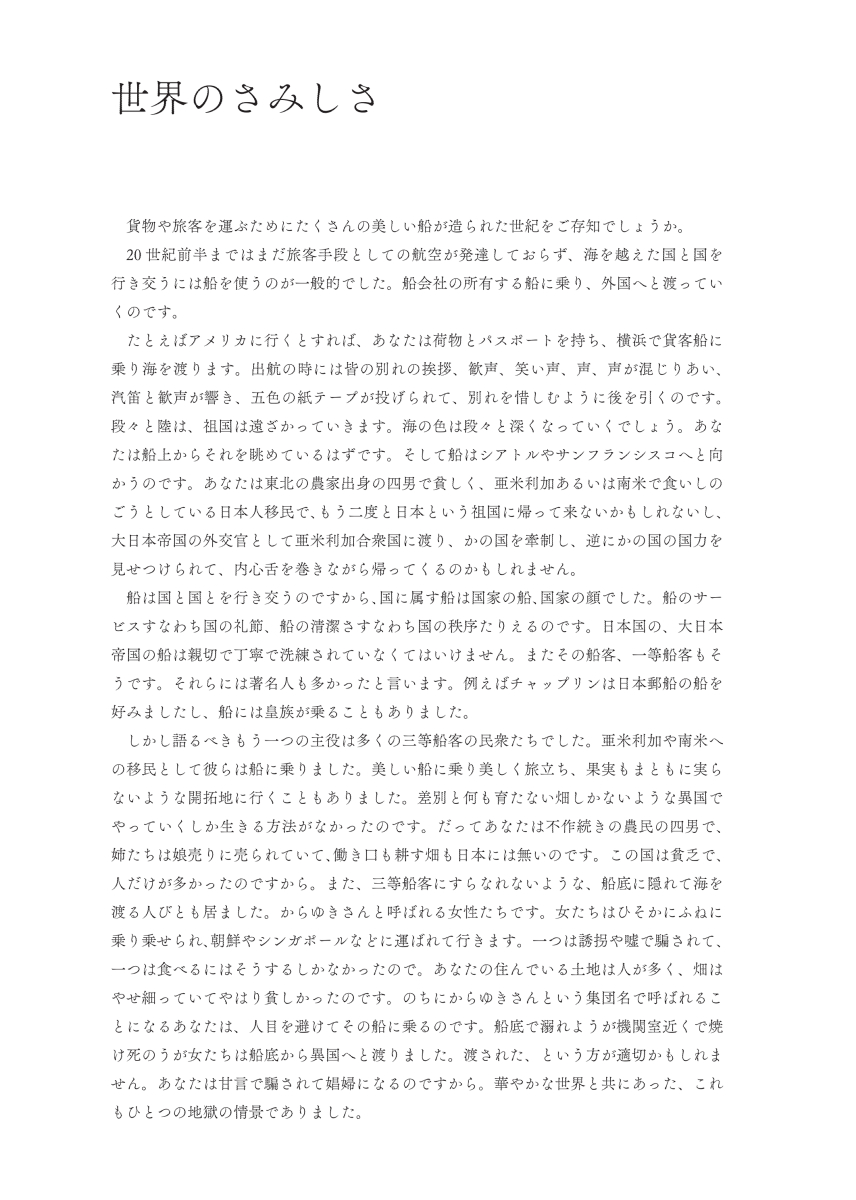
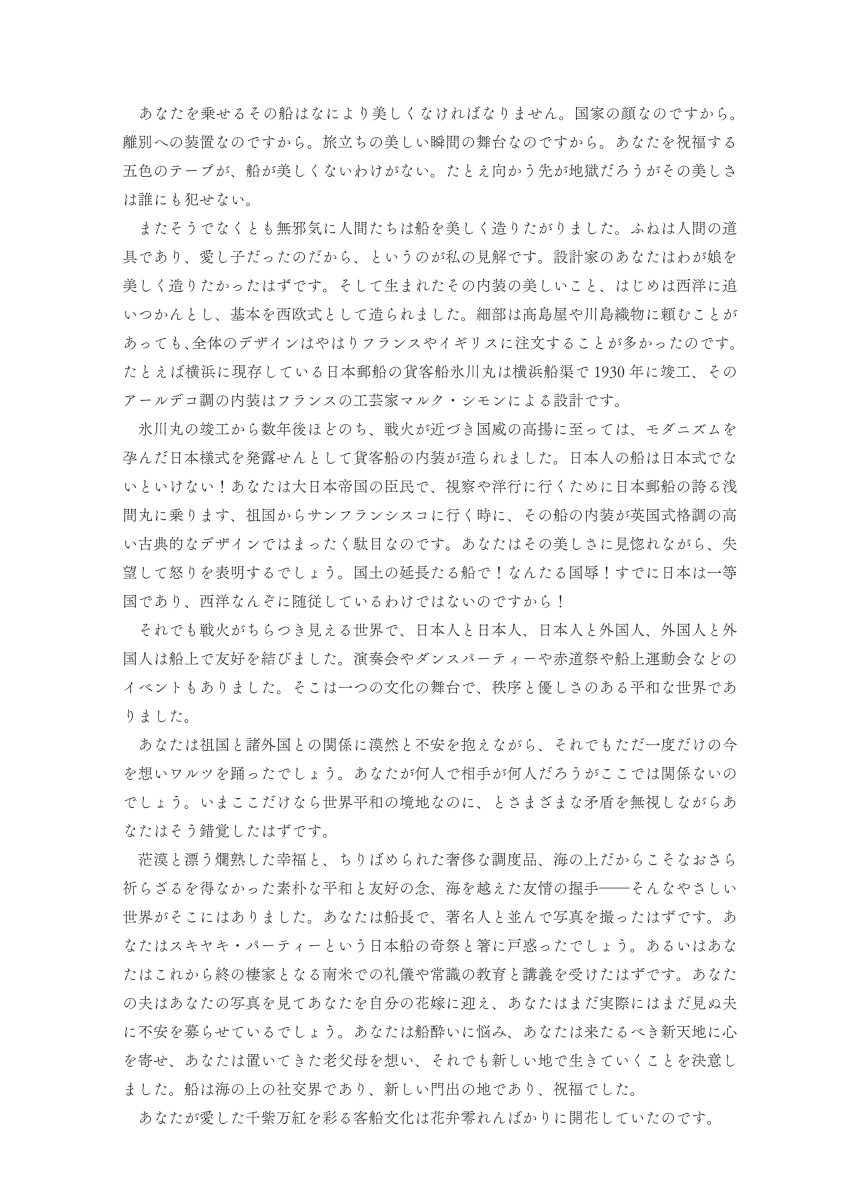
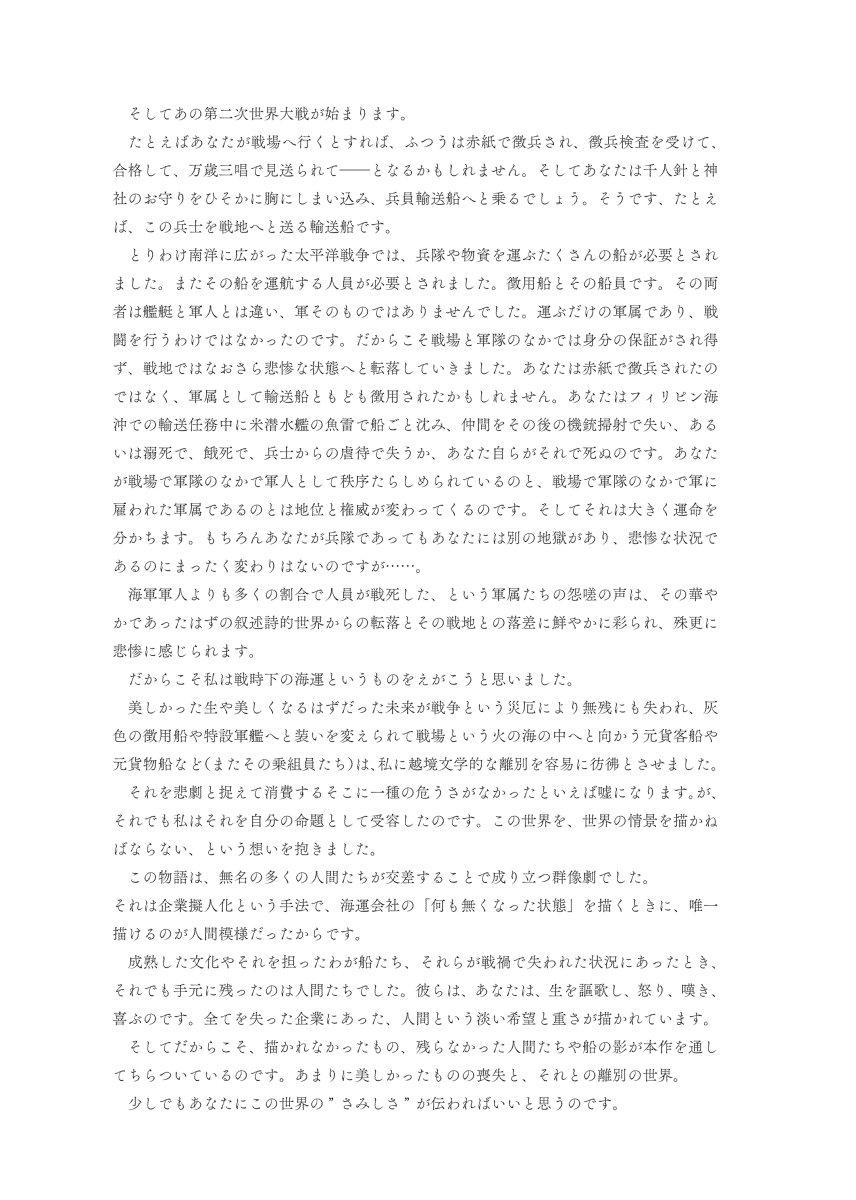
畳む
世界のさみしさ
貨物や旅客を運ぶためにたくさんの美しい船が造られた世紀をご存知でしょうか。
20世紀前半まではまだ旅客手段としての航空が発達しておらず、海を越えた国と国を行き交うには船を使うのが一般的でした。船会社の所有する船に乗り、外国へと渡っていくのです。
たとえばアメリカに行くとすれば、あなたは荷物とパスポートを持ち、横浜で貨客船に乗り海を渡ります。出航の時には皆の別れの挨拶、歓声、笑い声、声、声が混じりあい、汽笛と歓声が響き、五色の紙テープが投げられて、別れを惜しむように後を引くのです。段々と陸は、祖国は遠ざかっていきます。海の色は段々と深くなっていくでしょう。あなたは船上からそれを眺めているはずです。そして船はシアトルやサンフランシスコへと向かうのです。あなたは東北の農家出身の四男で貧しく、亜米利加あるいは南米で食いしのごうとしている日本人移民で、もう二度と日本という祖国に帰って来ないかもしれないし、大日本帝国の外交官として亜米利加合衆国に渡り、かの国を牽制し、逆にかの国の国力を見せつけられて、内心舌を巻きながら帰ってくるのかもしれません。
船は国と国とを行き交うのですから、国に属す船は国家の船、国家の顔でした。船のサービスすなわち国の礼節、船の清潔さすなわち国の秩序たりえるのです。日本国の、大日本帝国の船は親切で丁寧で洗練されていなくてはいけません。またその船客、一等船客もそうです。それらには著名人も多かったと言います。例えばチャップリンは日本郵船の船を好みましたし、船には皇族が乗ることもありました。
しかし語るべきもう一つの主役は多くの三等船客の民衆たちでしょう。亜米利加や南米への移民として彼らは船に乗りました。美しい船に乗り美しく旅立ち、果実もまともに実らないような開拓地に行くこともありました。差別と何も育たない畑しかないような異国でやっていくしか生きる方法がなかったのです。だってあなたは不作続きの農民の四男で、姉たちは娘売りに売られていて、働き口も耕す畑も日本には無いのです。この国は貧乏で、人だけが多かったのですから。また、三等船客にすらなれないような、船底に隠れて海を渡る人びとも居ました。からゆきさんと呼ばれる女性たちです。女たちはひそかにふねに乗り乗せられ、朝鮮やシンガポールなどに運ばれて行きます。一つは誘拐や嘘で騙されて、一つは食べるにはそうするしかなかったので。あなたの住んでいる土地は人が多く、畑はやせ細っていてやはり貧しかったのです。のちにからゆきさんという集団名で呼ばれることになるあなたは、人目を避けてその船に乗るのです。船底で溺れようが機関室近くで焼け死のうが女たちは船底から異国へと渡りました。渡された、という方が適切かもしれません。あなたは甘言で騙されて娼婦になるのですから。華やかな世界と共にあった、これもひとつの地獄の情景でありました。
あなたを乗せるその船はなにより美しくなければなりません。国家の顔なのですから。離別への装置なのですから。旅立ちの美しい瞬間の舞台なのですから。あなたを祝福する五色のテープが、船が美しくないわけがない。たとえ向かう先が地獄だろうがその美しさは誰にも犯せない。
またそうでなくとも無邪気に人間たちは船を美しく造りたがりました。ふねは人間の道具であり、愛し子だったのだから、というのが私の見解です。設計家のあなたはわが娘を美しく造りたかったはずです。そして生まれたその内装の美しいこと、はじめは西洋に追いつかんとし、基本を西欧式として造られました。細部は髙島屋や川島織物に頼むことがあっても、全体のデザインはやはりフランスやイギリスに注文することが多かったのです。たとえば横浜に現存している日本郵船の貨客船氷川丸は横浜船渠で1930年に竣工、そのアールデコ調の内装はフランスの工芸家マルク・シモンによる設計です。
氷川丸の竣工から数年後ほどのち、戦火が近づき国威の高揚に至っては、モダニズムを孕んだ日本様式を発露せんとして貨客船の内装が造られました。日本人の船は日本式でないといけない!あなたは大日本帝国の臣民で、視察や洋行に行くために日本郵船の誇る浅間丸に乗ります、祖国からサンフランシスコに行く時に、その船の内装が英国式格調の高い古典的なデザインではまったく駄目なのです。あなたはその美しさに見惚れながら、失望して怒りを表明するでしょう。国土の延長たる船で!なんたる国辱!すでに日本は一等国であり、西洋なんぞに随従しているわけではないのですから!
それでも戦火がちらつき見える世界で、日本人と日本人、日本人と外国人、外国人と外国人は船上で友好を結びました。演奏会やダンスパーティーや赤道祭や船上運動会などのイベントもありました。そこは一つの文化の舞台で、秩序と優しさのある平和な世界でありました。
あなたは祖国と諸外国との関係に漠然と不安を抱えながら、それでもただ一度だけの今を想いワルツを踊ったでしょう。あなたが何人で相手が何人だろうがここでは関係ないのでしょう。いまここだけなら世界平和の境地なのに、とさまざまな矛盾を無視しながらあなたはそう錯覚したはずです。
茫漠と漂う爛熟した幸福と、ちりばめられた奢侈な調度品、海の上だからこそなおさら祈らざるを得なかった素朴な平和と友好の念、海を越えた友情の握手――そんなやさしい世界がそこにはありました。あなたは船長で、著名人と並んで写真を撮ったはずです。あなたはスキヤキ・パーティーという日本船の奇祭と箸に戸惑ったでしょう。あるいはあなたはこれから終の棲家となる南米での礼儀や常識の教育と講義を受けたはずです。あなたの夫はあなたの写真を見てあなたを自分の花嫁に迎え、あなたはまだ実際にはまだ見ぬ夫に不安を募らせているでしょう。あなたは船酔いに悩み、あなたは来たるべき新天地に心を寄せ、あなたは置いてきた老父母を想い、それでも新しい地で生きていくことを決意しました。船は海の上の社交界であり、新しい門出の地であり、祝福でした。
あなたが愛した千紫万紅を彩る客船文化は花弁零れんばかりに開花していたのです。
そしてあの第二次世界大戦が始まります。
たとえばあなたが戦場へ行くとすれば、ふつうは赤紙で徴兵され、徴兵検査を受けて、合格して、万歳三唱で見送られて――となるかもしれません。そしてあなたは千人針と神社のお守りをひそかに胸にしまい込み、兵員輸送船へと乗るでしょう。そうです、たとえば、この兵士を戦地へと送る輸送船です。
とりわけ南洋に広がった太平洋戦争では、兵隊や物資を運ぶたくさんの船が必要とされました。またその船を運航する人員が必要とされました。徴用船とその船員です。その両者は艦艇と軍人とは違い、軍そのものではありませんでした。運ぶだけの軍属であり、戦闘を行うわけではなかったのです。だからこそ戦場と軍隊のなかでは身分の保証がされ得ず、戦地ではなおさら悲惨な状態へと転落していきました。あなたは赤紙で徴兵されたのではなく、軍属として輸送船ともども徴用されたかもしれません。あなたはフィリピン海沖での輸送任務中に米潜水艦の魚雷で船ごと沈み、仲間をその後の機銃掃射で失い、あるいは溺死で、餓死で、兵士からの虐待で失うか、あなた自らがそれで死ぬのです。あなたが戦場で軍隊のなかで軍人として秩序たらしめられているのと、戦場で軍隊のなかで軍に雇われた軍属であるのとは地位と権威が変わってくるのです。そしてそれは大きく運命を分かちます。もちろんあなたが兵隊であってもあなたには別の地獄があり、悲惨な状況であるのにまったく変わりはないのですが……。
海軍軍人よりも多くの割合で人員が戦死した、という軍属たちの怨嗟の声は、その華やかであったはずの叙述詩的世界からの転落とその戦地との落差に鮮やかに彩られ、殊更に悲惨に感じられます。
だからこそ私は戦時下の海運というものをえがこうと思いました。
美しかった生や美しくなるはずだった未来が戦争という災厄により無残にも失われ、灰色の徴用船や特設軍艦へと装いを変えられて戦場という火の海の中へと向かう元貨客船や元貨物船など(またその乗組員たち)は、私に越境文学的な離別を容易に彷彿とさせました。
それを悲劇と捉えて消費するそこに一種の危うさがなかったといえば嘘になります。が、それでも私はそれを自分の命題として受容したのです。この世界を、世界の情景を描かねばならない、という想いを抱きました。
この物語は、無名の多くの人間たちが交差することで成り立つ群像劇でした。
それは企業擬人化という手法で、海運会社の「何も無くなった状態」を描くときに、唯一描けるのが人間模様だったからです。
成熟した文化やそれを担ったわが船たち、それらが戦禍で失われた状況にあったとき、それでも手元に残ったのは人間たちでした。彼らは、あなたは、生を謳歌し、怒り、嘆き、喜ぶのです。全てを失った企業にあった、人間という淡い希望と重さが描かれています。
そしてだからこそ、描かれなかったもの、残らなかった人間たちや船の影が本作を通してちらついているのです。あまりに美しかったものの喪失と、それとの離別の世界。
少しでもあなたにこの世界の”さみしさ”が伝わればいいと思うのです。
2024年5月10日 この範囲を時系列順で読む

性愛の陥穽
アジア・太平洋戦争での船の大量喪失、という問題が語られる時によくよく厳しく問いただされるのは日本海軍の海上護衛思想の薄さや、その戦争の損失で鮮明に露呈した日本国家の計画性のなさです。あるいはあまたの華やかで剛健な大型船舶たちの沈没、あるいは軍人による船員の扱いの荒さは悲壮感を伴ってわたしたちの心を打ちます。戦場を主戦場としなかった人間たちの哀しい戦争の運命がそこにはある。多くの国籍の人々を貨客船に乗せた友情、見るも鮮やかなディナー、洗練された文化が一緒くたに灰色の塗装に化けること。絹ではなく軍需品を運ぶということ。殺意と機銃掃射。にんげんの深いかなしみとくるしみ。
けれど感情で見うしなってならないのは時代を俯瞰する冷静さなのかもしれません。戦後八十年からの、その俯瞰ができる立場を、擬人化という存在に投影して描いた物語が「大脱走」でした。
わたしがあの時代を俯瞰したときに捉えた感覚をよりいっそう複雑にしたのは、森崎和江が解題するような侵略、生活上の心情的な侵略行為という考えでした。彼女がからゆさきさんの主体性を語るときに言及するアジアの民衆との肌のあわせよう、アジアの民衆と彼女らで茶碗一杯の飯を奪い合うような関係。外国へ行き現地人を武器で殺し殺されることだけが戦争であり侵略ではない、という自責に駆られる森崎和江は植民地朝鮮生まれの女性でした。朝鮮の空は高くて美しい、空気が湿らず澄んでいると彼女が想うとき、背負ってくれたオモニの髪が唇についたことを思い出すときに、森崎和江はその愛情こそが他者を侵略していたという事実をひたと見つめます。戦時中に日本に帰ってきて、故郷であった朝鮮(植民地を故郷、と呼ぶこと自体が侵略的心情なのですが)に戦後帰れなくなった森崎和江は痛感します。その郷愁や愛そのものが罪だったということを。
森崎和江は関釜連絡船で日本へやってきたのでした。
**
のちのこと、老いたおキミがある日、渡り鳥の大群が飛来したのをみて、
「ああっ、この鳥!うちが朝鮮に売られていくとき、玄界灘で逢うたんよ。うちの肩にとまったんよ」と叫び、その夜眠らなかった。
(森崎和江『からゆきさん 異国に売られた少女たち』)
のちに娼婦の経験での心的外傷により精神病院で亡くなるおキミは、養女に出されからゆきとして大陸へと渡りました。神戸から貨物船に乗り、門司から玄界灘をとおり朝鮮へ。たくさんの連雀が九州へと渡っていくのが見えたらしい。鳥たちはおキミとは真逆の方向へ飛んだ。
からゆきたちと船とは切っても切れない縁です。航空機も鉄道も挟まる余地などない。二十世紀に海をわたるのですから。船に隠されて密航したからゆきたちは上手くいかなければ船底で、箱の中で、樽の中で、石炭庫内で死ぬことになります。上手くいっても海外で娼婦となるだけなのですが。日本船はおおかたは三十人ほどを乗せ、その利益は大きく、また密航の検査をするには石炭夫や火夫の気性は荒く、そうしてこれらの犯罪は報道されても止まらず、なによりも女たち自身が貧困からの脱出を夢見ていました。人買いから見せられた夢というものが真実だったかは別としてですが。それに誘拐によっても多くの少女たちがあつめられました。日本郵船の伏木丸では隠れた石炭庫に隣り合う火炉に燃やされて、多くの女たちが死んだらしい。からゆきになるまえに。この時、一八九〇年。
森崎和江が言うようなからゆきさんたちが行った心的侵略というものがあったとしたら、それらを運んだ船や船会社をどう捉えるべきだろう。彼――というものが擬人化創作では存在するのだけど――はその事象どう思っていたのでしょう。船によって運ばれたからゆきさんらはシンガポールに入港した大日本帝国海軍の艦艇に乗っていた軍人たちを好いひととして迎えていました。その威信は世界的なもので日本からとおい地にいるからゆきさんたちは誇らしく、また頼もしく思っていたことでしょう。この三者三様の関係をどう捉えたらいいのかと考えておりました。
#「大脱走」(企業擬人化)
2023年9月14日 この範囲を時系列順で読む
船で運ぶもの
Googleで「日本郵船歴史博物館」と検索すると検索候補に「恨み」と出てくるんですけど、あれ、結構びっくりしますよね。あれはおそらく博物館の展示である「戦争と壊滅」を指しているんだと思うんです。恨み、というのは商船がたくさん徴傭されたこと、その乗組員も取られたこと、その多くが返って/帰って来なかったことへの日本海軍と日本政府への非難のことでしょう。実際に皆さんが見たらちゃあんとわかったと思うのですけど、そこまで恨みってもんは書かれてなんかないんです。そこから日本郵船の恨みというものを感じるのは、むしろ私たちに後ろめたさがあるからじゃないのかしらん、とわたしは思っちゃいます。
敗戦後、事実上日本政府は企業に戦時補償をしませんでした。なぜならインフレを許さないGHQが補償を許さなかったからで、GHQが許さなかったという大義名分のもとで政府は補償をしない自身を許しました。もちろんもう少し事情は込み入るのだけど、とにかく補償はなくなちゃって、海運会社は踏んだり蹴ったりということで戦争は一応終わってしまいました。
戦争は終わりました。進駐軍が日本に来ました。占領下、といえばたとえば川島織物はアメリカ兵に大人気だったみたいなのです。珍しい織物や工芸品がいっぱいあったから。綺麗なものがいっぱいで。お土産品売りとして繁盛しました。あるいは工業の工場なら、日常用品を造ることでしのげたでしょう。鍋とか包丁とか。美しいものか実用的なものを。戦争には使わないものを。兵器を造ることは忘れて。
でも海運会社にはごはんの種の船がなかったから、船があっても外航できないから、まず本業はだめだったんです。印刷機とか船の大型洗濯機とかは残ってたみたいです。これでどうにかしのげないか、って話になってきます。たとえば洗濯屋をやるとか。貨客船文化で鍛えた接客業とか……。
なにより泡を食ったのは、商社と同じく、世界を跳躍した日本海運が……それらが集めた資金が、軍国の地位を押し上げたのではないか、という連合国側の考えとそこから由来する厳しい対応でした。商社の三井物産は解体されちゃったし、まあ日本郵船もねえ……みたいな話はあったみたいなんです。こういう企業がね。帝国を根強く支えた資本がねえ。三井三池鉱山があったことがどういうことかっていうとね。考えないとね。じゃあさ……。みたいなことになっていくんでしょうか。アメリカはそこまで考えてなかったと思うのだけど。でも、海運会社にその歴史を俯瞰できる、たとえばそう、擬人化のようなものがいれば、そこまで考えていたかもしれない、ですよね。物と人を運んでいくことの宿痾を。船で。船を使って。
公娼制と船ってふかく結びついていると思いませんか、とひとに提示する時に、脳裏にあるのは「からゆきさん」やそれに部類する多くの移民や流民や棄民です。明治時代の日本企業による海外進出は、まず三井物産が進出し、日本郵船が航路を通し、横浜正金銀行が支店を出すものだ、といわれていたけども、企業の進出のまわりにいて、それらを使う人びとがいっぱいいたはずなんです。もちろんからゆきさんたちは日本郵船の秘蔵っ子の貨客船なんて使わないのだろうけど、そうじゃなくて、そうじゃなくてわたしがしているのは、企業の手からこぼれおちたおおくの庶民のはなしです。小さな会社の小さな貨物船の船底に身をひそめて、時には溺れ死んでも、その手段を頼って密航せざるをえなかった民衆たちのはなしです。三等客室にすらなれなかったひとびとを、ときどき、企業擬人化たちはちゃんと思い出しているかもしれませんね。「妻の母はからゆきさんだった」とウィーンのある教授から手紙が送られてきたことがある、と書き残したのは『からゆきさん』を著した森崎和江でした。私はそれを読んだとき、その妻の父は誰だったのだろうか、妻の血筋は日本人だったのだろうか、その教授はどのような人種なのだったのだろうか、彼らに子どもはいるのだろうか、その彼あるいは彼女はどんな容貌をしているのだろうかと思い、またそれらの疑問はあの広大な大陸では何の意味もないのかもしれないと一人納得したんです。島国の向こうの大陸では国境は上に移ろい下へと侵攻し、また近代になって国家間で厳密に定められ、時には戦争で喪失し……ということが当たり前にあった、「からゆきさん」のいきついたマレーシアや朝鮮などの大陸の都はオーストリアの首都ウィーンへとはるばる連なっていきます。またそれは大陸だけのはなしではなく、この島国もそうした大陸の確かな一員であったこと、みはてぬ海とそこにあった陸はなにより広くてまた近かったこと、そのことを重々熟知していたのはやはり海運会社だったはずでしょう。あやしい混血の色彩と国籍の飽和は彼らのたしかに知る世界でした。その世界はきっとある意味でうつくしかったはずです。が、彼らの罪もそこから発したものでした。国家が国民の地位を担保する時代で、その寄り辺を持たなかった「からゆきさん」や移民たちは、渡った先の外国では容易に弱者へと転落していきました。そのことを承知しながらも、船で運ぶことが生業でした。なぜならそこに、資本と利益があったから。収益という存在意義が。
利益を追い求めた結果、軍国へと貢献し、その国家と軍は自らに船と犠牲とを求めました。けどその船と犠牲とは時に己に確固たる地位と利潤を由来させる可能性もあったんです。信濃丸はやっぱり誇らしかったことを、やっぱり憶えていたかもしれませんね。脆さをたたえた多くの戦標船を前にしてもその夢は崩れなかったかもしれない。なぜなら犠牲の先には、終わりと救済があったはずだから。まだこの苦しみの終わりとその補償の可能性はあった。わずかでも希望はあった。……はずでした。
私が求めたのは、そういった自らの罪と業の自覚と、それでもそこを進むしかなかったことを自認していた企業と、その未来と救済とが失われることになったはなしでした。戦争は終わったけれど、べつの戦争は終わっていないはなしでした。その戦争に嬉々と加担した自分とその自覚性のはなしでした。「大脱走」の主題の一つはそこにあるのです。
#「大脱走」(企業擬人化)
Googleで「日本郵船歴史博物館」と検索すると検索候補に「恨み」と出てくるんですけど、あれ、結構びっくりしますよね。あれはおそらく博物館の展示である「戦争と壊滅」を指しているんだと思うんです。恨み、というのは商船がたくさん徴傭されたこと、その乗組員も取られたこと、その多くが返って/帰って来なかったことへの日本海軍と日本政府への非難のことでしょう。実際に皆さんが見たらちゃあんとわかったと思うのですけど、そこまで恨みってもんは書かれてなんかないんです。そこから日本郵船の恨みというものを感じるのは、むしろ私たちに後ろめたさがあるからじゃないのかしらん、とわたしは思っちゃいます。
敗戦後、事実上日本政府は企業に戦時補償をしませんでした。なぜならインフレを許さないGHQが補償を許さなかったからで、GHQが許さなかったという大義名分のもとで政府は補償をしない自身を許しました。もちろんもう少し事情は込み入るのだけど、とにかく補償はなくなちゃって、海運会社は踏んだり蹴ったりということで戦争は一応終わってしまいました。
戦争は終わりました。進駐軍が日本に来ました。占領下、といえばたとえば川島織物はアメリカ兵に大人気だったみたいなのです。珍しい織物や工芸品がいっぱいあったから。綺麗なものがいっぱいで。お土産品売りとして繁盛しました。あるいは工業の工場なら、日常用品を造ることでしのげたでしょう。鍋とか包丁とか。美しいものか実用的なものを。戦争には使わないものを。兵器を造ることは忘れて。
でも海運会社にはごはんの種の船がなかったから、船があっても外航できないから、まず本業はだめだったんです。印刷機とか船の大型洗濯機とかは残ってたみたいです。これでどうにかしのげないか、って話になってきます。たとえば洗濯屋をやるとか。貨客船文化で鍛えた接客業とか……。
なにより泡を食ったのは、商社と同じく、世界を跳躍した日本海運が……それらが集めた資金が、軍国の地位を押し上げたのではないか、という連合国側の考えとそこから由来する厳しい対応でした。商社の三井物産は解体されちゃったし、まあ日本郵船もねえ……みたいな話はあったみたいなんです。こういう企業がね。帝国を根強く支えた資本がねえ。三井三池鉱山があったことがどういうことかっていうとね。考えないとね。じゃあさ……。みたいなことになっていくんでしょうか。アメリカはそこまで考えてなかったと思うのだけど。でも、海運会社にその歴史を俯瞰できる、たとえばそう、擬人化のようなものがいれば、そこまで考えていたかもしれない、ですよね。物と人を運んでいくことの宿痾を。船で。船を使って。
公娼制と船ってふかく結びついていると思いませんか、とひとに提示する時に、脳裏にあるのは「からゆきさん」やそれに部類する多くの移民や流民や棄民です。明治時代の日本企業による海外進出は、まず三井物産が進出し、日本郵船が航路を通し、横浜正金銀行が支店を出すものだ、といわれていたけども、企業の進出のまわりにいて、それらを使う人びとがいっぱいいたはずなんです。もちろんからゆきさんたちは日本郵船の秘蔵っ子の貨客船なんて使わないのだろうけど、そうじゃなくて、そうじゃなくてわたしがしているのは、企業の手からこぼれおちたおおくの庶民のはなしです。小さな会社の小さな貨物船の船底に身をひそめて、時には溺れ死んでも、その手段を頼って密航せざるをえなかった民衆たちのはなしです。三等客室にすらなれなかったひとびとを、ときどき、企業擬人化たちはちゃんと思い出しているかもしれませんね。「妻の母はからゆきさんだった」とウィーンのある教授から手紙が送られてきたことがある、と書き残したのは『からゆきさん』を著した森崎和江でした。私はそれを読んだとき、その妻の父は誰だったのだろうか、妻の血筋は日本人だったのだろうか、その教授はどのような人種なのだったのだろうか、彼らに子どもはいるのだろうか、その彼あるいは彼女はどんな容貌をしているのだろうかと思い、またそれらの疑問はあの広大な大陸では何の意味もないのかもしれないと一人納得したんです。島国の向こうの大陸では国境は上に移ろい下へと侵攻し、また近代になって国家間で厳密に定められ、時には戦争で喪失し……ということが当たり前にあった、「からゆきさん」のいきついたマレーシアや朝鮮などの大陸の都はオーストリアの首都ウィーンへとはるばる連なっていきます。またそれは大陸だけのはなしではなく、この島国もそうした大陸の確かな一員であったこと、みはてぬ海とそこにあった陸はなにより広くてまた近かったこと、そのことを重々熟知していたのはやはり海運会社だったはずでしょう。あやしい混血の色彩と国籍の飽和は彼らのたしかに知る世界でした。その世界はきっとある意味でうつくしかったはずです。が、彼らの罪もそこから発したものでした。国家が国民の地位を担保する時代で、その寄り辺を持たなかった「からゆきさん」や移民たちは、渡った先の外国では容易に弱者へと転落していきました。そのことを承知しながらも、船で運ぶことが生業でした。なぜならそこに、資本と利益があったから。収益という存在意義が。
利益を追い求めた結果、軍国へと貢献し、その国家と軍は自らに船と犠牲とを求めました。けどその船と犠牲とは時に己に確固たる地位と利潤を由来させる可能性もあったんです。信濃丸はやっぱり誇らしかったことを、やっぱり憶えていたかもしれませんね。脆さをたたえた多くの戦標船を前にしてもその夢は崩れなかったかもしれない。なぜなら犠牲の先には、終わりと救済があったはずだから。まだこの苦しみの終わりとその補償の可能性はあった。わずかでも希望はあった。……はずでした。
私が求めたのは、そういった自らの罪と業の自覚と、それでもそこを進むしかなかったことを自認していた企業と、その未来と救済とが失われることになったはなしでした。戦争は終わったけれど、べつの戦争は終わっていないはなしでした。その戦争に嬉々と加担した自分とその自覚性のはなしでした。「大脱走」の主題の一つはそこにあるのです。
#「大脱走」(企業擬人化)
- 「渺渺録」(企業擬人化)(281)
- 『マーダーボット・ダイアリー』(41)
- おふねニュース(40)
- 「ノスタルジア 標準語批判序説」(二次創作)(23)
- 「大脱走」(企業擬人化)(23)
- SNSの投稿(19)
- 書籍情報(19)
- 『ハリー・ポッター』(17)
- 展示会情報(16)
- 読了(16)
- 「海にありて思うもの」(艦船擬人化)(16)
- 実況:初読『天冥の標』(16)
- 読んでる(15)
- きになる(13)
- 企業・組織(11)
- 船舶装飾考(10)
- DTT(DeskTopTeseihon)(8)
- 三菱重工さん関係のロケット(8)
- 御注文(8)
- 「蛇道の蛇」(一次創作)(8)
- 日本郵船歴史博物館再開館の軌跡(7)
- 「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)(6)
- 本(6)
- 「時代の横顔」(企業・組織擬人化)(6)
- 「空想傾星」(『マーダーボット・ダイアリー』)(6)
- 「徴用船の収支決算」(一次創作)(5)
- おふね(5)
- 映画(3)
- 国会図書館にない本(3)
- の部分(3)
- 感想『日本郵船戦時船史』(3)
- 模写(2)
- 漫画(2)
- 入手(2)
- 『ムヒョとロージーの魔法律相談事務所』(2)
- 「『見果てぬ海 「越境」する船舶たちの文学』」(艦船擬人化)(2)
- 「人間たちのはなし」(艦船擬人化)(2)
- 『青春鉄道』(2)
- 大谷印舗(1)
- 「水兵のリーベ」(一次創作)(1)
- 展示(1)
- 展示会(1)
- ハリー・ポッター(1)
- 映像(1)
- 「テクニカラー」/「白黒に濡れて」(艦船擬人化)(1)
- 「かれら深き波底より」(一次創作)(1)
- マーダーボット・ダイアリー(1)
野蛮な時代の波の上に彼女たちは揺蕩う、といえばそれは少し違うかもしれない。二十世紀までの人間たちはいつ如何なる時も野蛮であったし、ふねはそれらと共にあっただけであった。何度も続いてきた野蛮のとりわけ野蛮な時代に彼女らは揺蕩う。そして彼女ら、多くは1930年から後半にかけて勢ぞろいした日本商船隊にとっての"とりわけ野蛮"は太平洋戦争であった。
この試みは一つの仮定である。ふねたちに人間の似姿がいたとしたら、という突飛な仮定にすぎない。ただその仮定により滲み出てくる可能性を描いていきたい。戦場だった海に、いまはただ鉄屑として沈んでいる艦船たちを、つむぐ言葉と引く線でまるで生きていたかのように形容し、飾りたて、白黒の映像と写真の世界に色を添え、音があるように描写し、匂いを錯覚させ、彼女らの属していた海を描き、彼女らが自由だった海を描き、海を荒立たせは彼女らを溺れさせ波を荒立てせては小舟のように翻弄させ、あるいはその波間のうえでの誇りを描き、繁栄させては彼女らを微笑ませ衰退させては彼女らを沈黙させる、そのことにより、なにかしらの視点が生まれるのではないか。たとえば、そこにあったはずの数多の生への視点とか。
この物語の多くは「海を荒立たせは彼女らを溺れさせ波を荒立てせては小舟のように翻弄させ」「衰退させては彼女らを沈黙させる」時代を描いたものになるだろう。だがその中にも幸福や栄光、ちょっとしたきらめき、うつくしいものがあった。その一欠片を一欠片ずつ拾い集める作業のような物語でありたい。また、うつくしかったものとうつくしかったもの、あったものとなくなってしまったもの、その落差を色彩、いわば黄金時代の極彩と戦時下の灰色で描いていく。もちろん"灰"とは戦争、軍属、特設の艦艇、軍艦である状態に置かれたことの隠喩である。
彼女らはそれぞれの顔があるだろう。幸せな表情や、苦悩に満ちた顔をするだろう。うつくしい顔をするだろう。しかしそう考えたときに思い浮かんだのは、現実と追憶の急激な落差についていけず笑うしかなかった人間たち、そしてふねたちの引き攣った笑み、それのみであった。
#「病院船の顛狂室」(艦船擬人化)