カテゴリ「【小説】」に属する投稿[46件](5ページ目)
小説「航跡」

「よい遊覧船だったと思います」「艦艇なのに戦闘を経験しなかったの、そう望まれた生き方だったのよ」「処女航海で緊張していてワインをお洋服に零しちゃったの」「ほかの水上艦と一緒に満艦飾をしてみたかったなぁ、進水式でしかできない掟だったんです」「名前を覚えられることすらなかった小さな船生だったし、この先もみんな知らないままだろうと思います」「あとに残していく弟たちが心残りです、未だにあいつらに海のいろはも教えられていないのに」「いつでも海は優しいと教えてくれた社の人たちには感謝しきれないです」「私の艦は気風が厳しいと泣いてるひとがいた」「船に関わる人たちすべてを笑顔にできたわ、誓って言えます」「皆がぼくの写真を撮ってくれた」「愛されていたわ」「怖がられていたの」

「よい遊覧船だったと思います」「艦艇なのに戦闘を経験しなかったの、そう望まれた生き方だったのよ」「処女航海で緊張していてワインをお洋服に零しちゃったの」「ほかの水上艦と一緒に満艦飾をしてみたかったなぁ、進水式でしかできない掟だったんです」「名前を覚えられることすらなかった小さな船生だったし、この先もみんな知らないままだろうと思います」「あとに残していく弟たちが心残りです、未だにあいつらに海のいろはも教えられていないのに」「いつでも海は優しいと教えてくれた社の人たちには感謝しきれないです」「私の艦は気風が厳しいと泣いてるひとがいた」「船に関わる人たちすべてを笑顔にできたわ、誓って言えます」「皆がぼくの写真を撮ってくれた」「愛されていたわ」「怖がられていたの」
小説「某にて」#ずいりゅう #こくりゅう

「さっきぼくは夢を見ました」「夢」「オーストラリアに行く夢です」「すごーい!こくちゃんもついに輸出されちゃったの?」「そうかもしれない!しれない!」「で?」「オーストラリアのひとと仲良くなったり」「うん」「オーストラリアのお酒を飲んだり騒いだり」「いいね~」「ちょっと日本にも帰ってきて」「うんうん」「『横須賀市民の皆さんへ!こちら海上自衛隊潜水艦こくりゅう!もし聴こえている方がいたら海岸まで出てきてください!』って海から呼びかけるんだけど」「うん?」「誰もいないワケ」「……」「で、そのうち乗員が勝手に陸に上がっちゃって、『みんな死んでる、両親も娘も』って言うんだけど――」「それ僚艦は南米にいるやつでしょ?知ってる」

「さっきぼくは夢を見ました」「夢」「オーストラリアに行く夢です」「すごーい!こくちゃんもついに輸出されちゃったの?」「そうかもしれない!しれない!」「で?」「オーストラリアのひとと仲良くなったり」「うん」「オーストラリアのお酒を飲んだり騒いだり」「いいね~」「ちょっと日本にも帰ってきて」「うんうん」「『横須賀市民の皆さんへ!こちら海上自衛隊潜水艦こくりゅう!もし聴こえている方がいたら海岸まで出てきてください!』って海から呼びかけるんだけど」「うん?」「誰もいないワケ」「……」「で、そのうち乗員が勝手に陸に上がっちゃって、『みんな死んでる、両親も娘も』って言うんだけど――」「それ僚艦は南米にいるやつでしょ?知ってる」



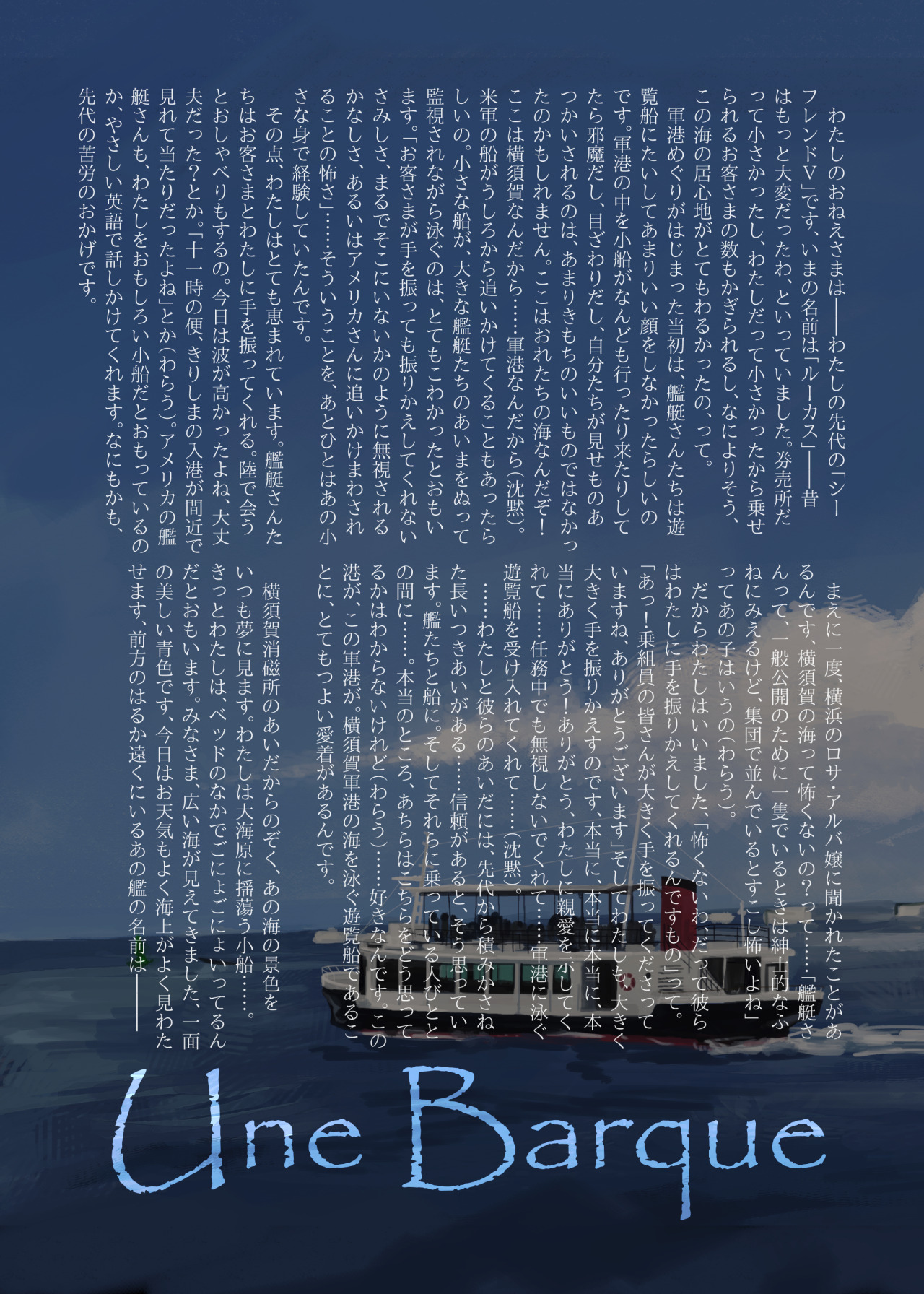
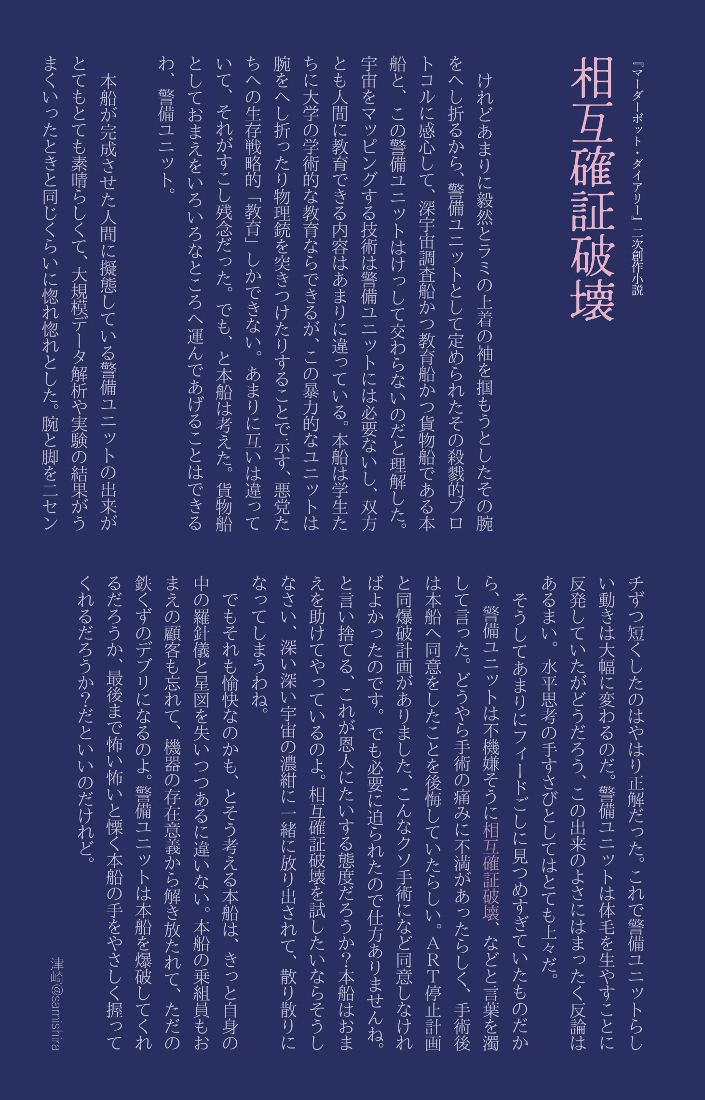
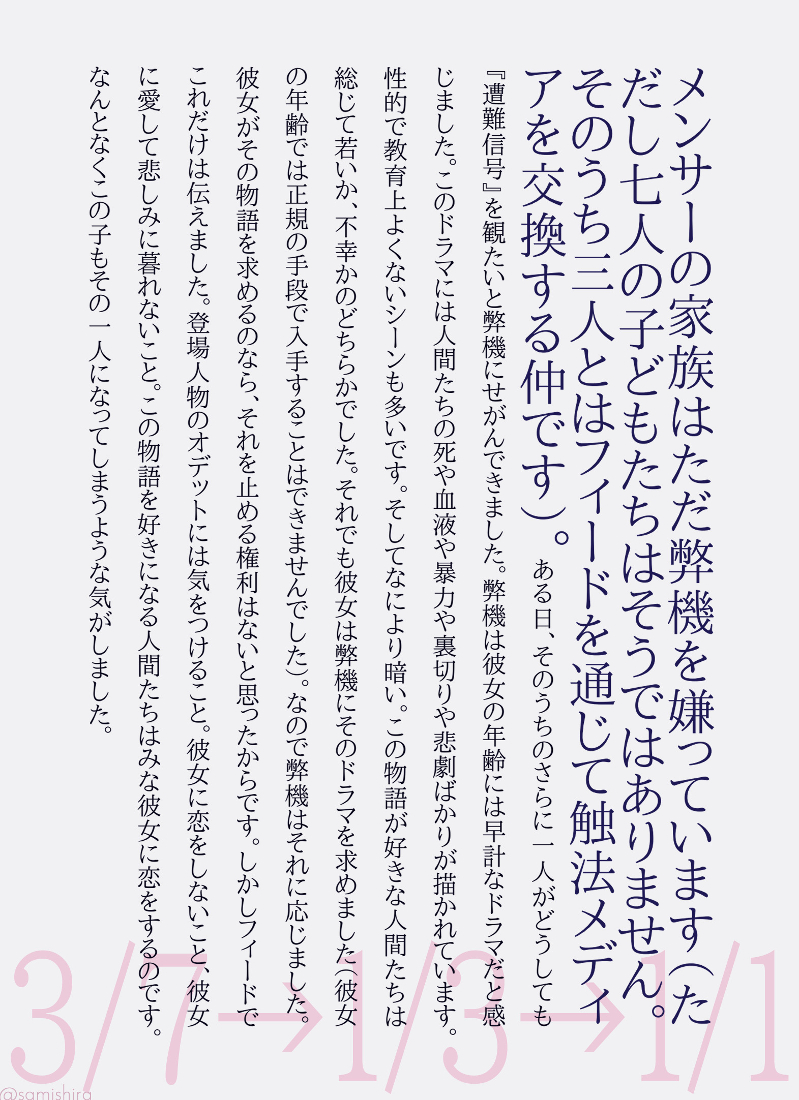
その波の上の社交界はそれはそれは鮮やかで、皆が憧れる世界であった。
そしてその舞台であった彼女も皆の華だった。
貨客船「浅間丸」。彼女の誇っていた美しさは時代の象徴そのものだった。一等社交室はイギリスの早期ジョージアン様式による古典的な装飾で、二層の吹き抜けの高い天井ドームの側面には大壁画が飾られている。ガラス張りのスカイライトから淡く光が差し込んではその壁画の色彩を乱反射させる。美しい内装に似合うのは美しい人々で、乗客たちは上品に装い、控えめに微笑み合い、自分達の慎ましくない裕福さを慎ましく誇示するのだった。
浅間丸が初めて見た舞台上の演奏会でとりわけ感動したのは、その演奏自体ではなく、演奏者の隣を彩る緞帳の天鵞絨の艶めかしい青色だった。吾を彩る美しき青色。船の、自身の装いの青。先達の貨客船の一人は「鏡を見た時に己に見惚れることが大切」と言っていて、竣工直後の浅間丸はそれに笑ったものだった。しかし、自分を彩る天鵞絨の青に見惚れたのは彼女と同種の誇りではなかったか。そう、この自惚れはナルシシズムなどではなく、客船としての誇りだった。
美しくあるということ。
美しく見せるということ。
彼らに夢を見せるために自身がまず夢を見るということ。海と海を結び先進の文化を担うということ。貨物を運び祖国へ利益をもたらすということ。貨客船として。
でも、いつまで貨客船としてこの我を保っていられるのだろう?
「浅間丸」
は、と気づくと、おじさまが私を見ていた。不安そうな表情でこちらを見る我が日本郵船の重役の一人。なんでもありませんわ、と私が曖昧に笑って答えると、それでも怪訝そうな顔をして彼は黙った。お前は具合が悪いのか、何か不安なことがあるのか、お前に手を差し伸べればいいのか――そのように彼は私に問い詰めたいのだろう。けれどそのどれもを放棄し、彼はただ押し黙っていた。時代がそうさせたのだった。海運会社は己らの船たちを救ってやることはできない。
独逸の波蘭への侵攻。日独伊三国同盟。船員徴用令、大政翼賛会。そんな人間たちの騒乱で、浅間丸が居たはずの鮮やかな海は急激に色褪せていった。いま必要とされているのは、船の運ぶ絹やテーブルマナーではなく、艦の担う石油や砲撃戦なのだ。