カテゴリー: 1-2企業・組織/企業・組織擬人化
-

潰えた幻影:「大脱走」第4話
企業擬人化>「大脱走」>第四話「潰えた幻影」
-

企業・組織擬人化創作漫画「河原」(「渺渺録」)
フネの在りどころ。 Bluesky X 企業・組織擬人化>企業・組織擬人化創作漫画「渺渺録」>「河原」
-

多くの面影:「大脱走」第5話
企業擬人化>「大脱走」>第五話「多くの面影」
-

いま再びの地獄:「大脱走」第6話
企業擬人化>「大脱走」>第六話「いま再びの地獄」
-

それから:「大脱走」第7話
企業擬人化>「大脱走」>第七話「それから」
-
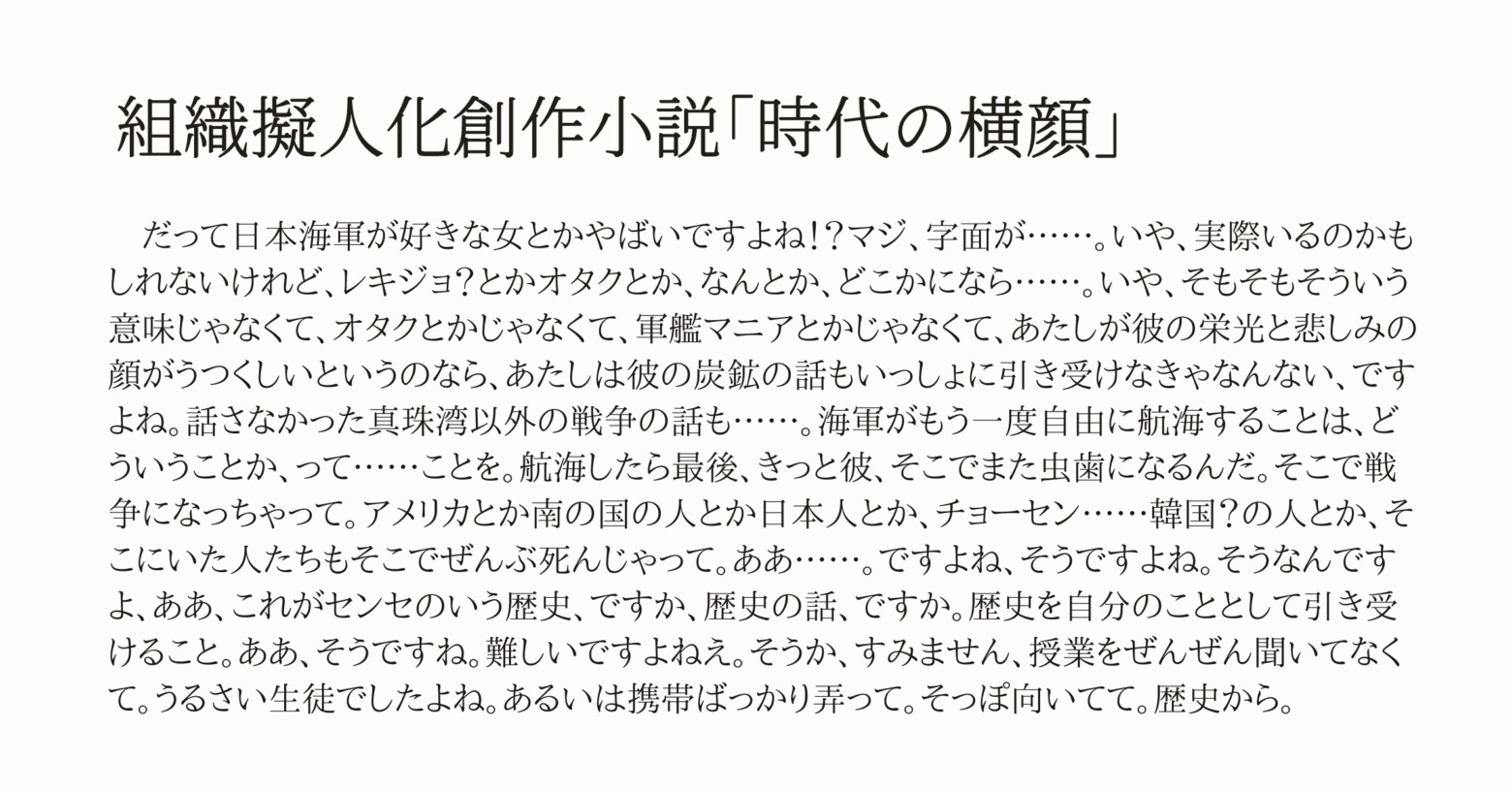
組織擬人化創作小説「時代の横顔」
あのう……ですね……。その、先生を、先生を今日、お呼びしたのは、というか、ごはんに誘ったのは、中学校時代の教…
